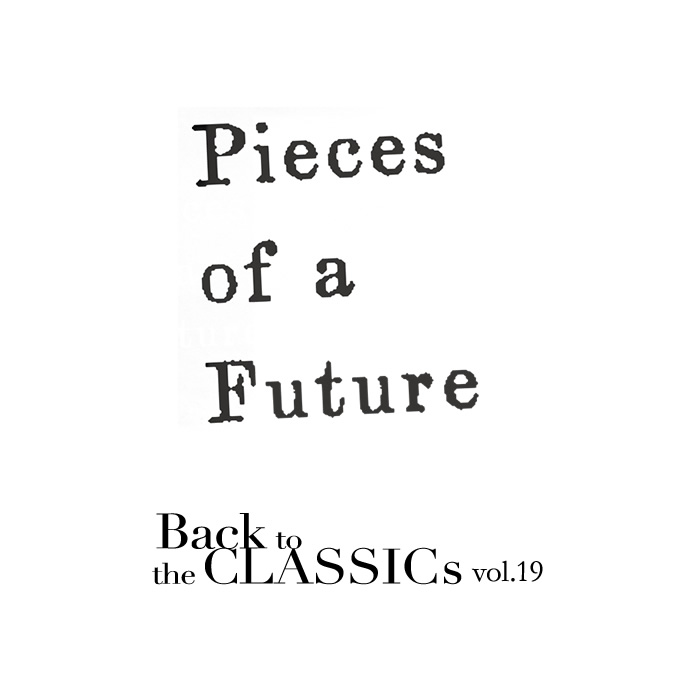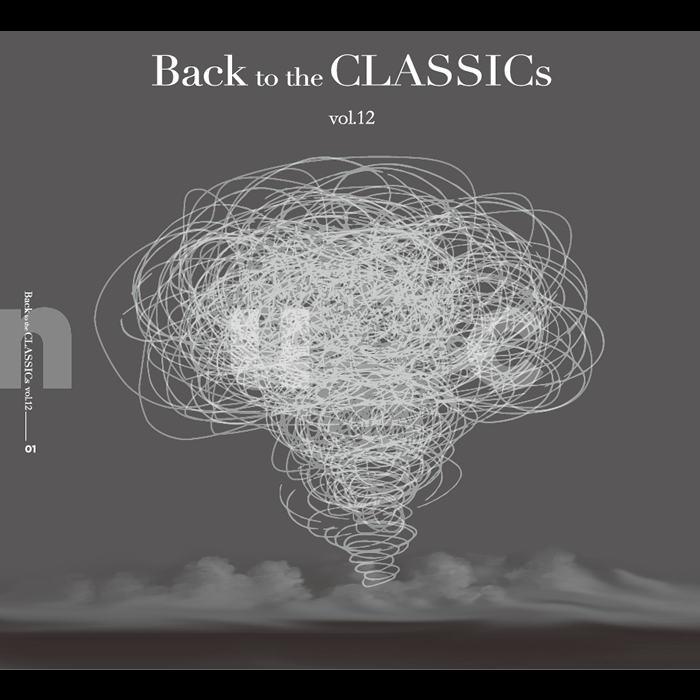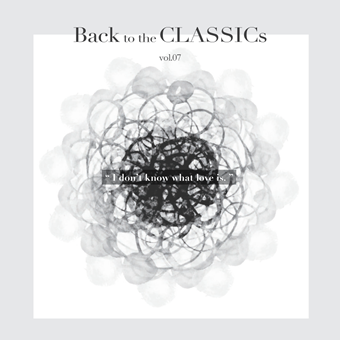Back to the CLASSICs vol.14 戦争の記憶
今号のテーマは「戦争の記憶」。だが、これはよくよく考えると奇妙なことだ。なぜなら記憶とは一般的に、経験した物事を心にとどめ覚えておくことだからだ。私を含め執筆者たちは現在二十代。そう、誰も直接的には戦争を経験していない。
では、この記憶とは一体?
そこにはまず一つの結論がある。「私たちは誰も戦争の記憶を語れない」。つまり、この試みは不可能であるというところから出発しなければならない。
しかし私たちの中にこそ戦争の記憶はないが、それを経験した「誰かの記憶」ならば存在する。それは手記であったり、物体であったり、映像であったりする。そこから私たちは様々なことを学ぶことができる。
だが私たちは学ぶのではなしに、やはり思い出す必要があるだろう。戦争から遠く時が隔たり、そのリアリティもすっかり薄れた世界に生きる私たちは、こう考えてみなければならない。あのとき死んだのは私かもしれなかった、と。日常を奪われ、自由を奪われ、果ては命を奪われたということを思い出す必要があるのだ。
それはつまり、彼らが残したものを辿り、その記憶を「引き受ける」ことに他ならない。
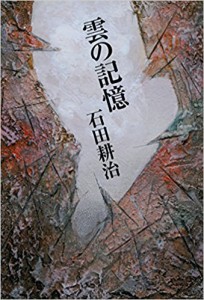
石田 耕治
『雲の記憶』
河出書房新社 2014 年
「流れと叫び」
「人影の石」をご存知だろうか。原爆の爆心地から260 メートルの位置にあった住友銀行広島支店入り口の石段に熱線で焼きつけられた人の影である。そのため「死の人影」とも呼ばれている。
摂氏3000~4000 度にもなる高熱で身を焼かれるという私たちには想像もつかないようなその死に方をはっきりと地上に残る痕跡として提示している点で見るものに強い印象を残す。現在は平和記念資料館に保存されているが、しかし風化は避けられるものではなく、影は時を経るにつれ次第に薄くなってゆく。これはその痕跡が私たちに惨状を想起させる非常に強い契機になるのと引き換えの致命的な点でもある。この人影の石も現在広島平和記念資料館のデータベースで閲覧できる写真を見ると、影が薄くなっているのが分かる。実際この石の資料館での保存が開始されたのは1971 年となっており、原爆の投下からかなり後になってからのことである。
今でこそ展示物となったこの石が、復興していく街の片隅で忘れ去られていく時代があった。それを描いた小説がある。石田耕治という原爆をテーマに小説を書き続けた作家が1961 年に発表した「流れと叫び」という作品だ。
この作品の主人公である「彼」は「人影の石」の主として登場する。もちろん、実際にはこの人影の主は亡くなっているし、正確には誰なのかも判明していないので死者として、だ。地上に自らの痕跡が残ってしまったことで、それを地上にとどまる権利のようなものとして捉えてしまい、そのため回想にすがり、死にきれないでいる元銀行員として影の主は描かれる。残された影に寄り添うようにして過ごし、薄れゆく影を守る意識でそこにとどまり続けているが、生きている人間に関わることはできない。
一方で街には名もなき死者たちもとどまっている。彼らは地上に痕跡もなく、人影の石ですら生きている人々の目を引くことの少なくなった現在では、なお忘れ去られつつある存在だ。しかし彼らはそうした忘却に抗って、結託してある「流れ」を自分たちの手で起こそうと企てている。地上に跡が残った「彼」は何も残すことなく死んでいった死者たちからしてみればいわば特権的であり、そのことで反感を買っていたのだ。影が薄れつつある今、
お前も我々と同じ平凡で、人々から忘れ去られようとしている死者の一人として「流れ」を起こすのを手伝うべきだ、と。しかし「彼」は誰からも忘れ去られ真に孤独になることへの恐怖から自らの影に固執する。
そんなある時、「彼」は自らを「原爆の子」と名乗る子どもたちと出会う。子どもたちは街を徘徊する死者の群れと異なり新しく生まれたのだという。つまり忘れ去られるものとしての死者ではなく、新たに思い出されるものとしての死者として描かれている。だが、その子どもたちも死者の「流れ」に巻き込まれ散り散りになってしまう。
死者たちが度々口にするこの「流れ」とは一体何なのか。作中では一度も確かなことは明らかにされない。だが、物語の最後にこういった台詞がある。
この思い出してくれという言葉は、目覚ましい復興の代償として忘れ去られていく死者たちの悲痛に満ちた叫びである。おそらく流れとは忘却としての復興ではなく、われわれ死者に寄り添い生きていく道を探ってほしいとの願いなのだ。しかしそれが新しく生まれた子どもたちをも巻き込んだとなれば、そこには何より忘れられることへの強い憤りが見てとれる。
最後には「彼」も、この流れがきっと街の生きている人々の目を覚ますであろうことを確信し、それに合流しようとするところで物語は終わっている。
実際に痕跡として残った人影。そこから想像力を駆使し、死者に語らせる。だがこれはおかしなことだ。実際には死者は語らない。今私たちに語りかけることができるのは死者が残したものだけだ。しかし何の痕跡もなく地上から姿を消してしまったものは本当に存在していたのかどうかももはや分からない。
あの日石段に腰掛けていたものは影がその存在を覚えていた。だがそれもいつか消えるとするなら、その時生きている人々はどうするのか。思い出す手立てが何一つない死者をそれでも思い出すこと。
何も残さず死んでいった人。そのため存在していたのかも分からない人。だが、彼らは存在し、生きて、そして無残に死んでいった。それは理解することなのか、あるいは信じることなのか。
時間が加速し、情報が錯綜する現代だ。その中で、この名もなき死者をこそ想起することは忘却への抵抗の正念場だと思える。
 小林 卓哉
小林 卓哉
1992年生まれ。大学在学中、保坂和志とロラン・バルトに感銘を受け文学に強い興味を抱く。
現在都内で販売員をする傍ら執筆中。

古井 由吉
しろわだ 『白暗淵』
講談社文芸文庫2016 年(単行本は2007 年)
どうして歌を歌うのだろうか。歌といえば、私たちの時代ならば四、五分ほどのポップスやクラブ音楽を思い浮かべる人が多いかもしれない。歌はそれほど僅かな時間で聴き終わり、すぐにでもわかり、効き始めるような心地がする。しかし存外、歌うことには時間がかかる。
幾度となく反復して聴いた歌の、ある日、道すがらに、或いは友人と待ち合わせた折に通りすがる人を眺めながらの漠とした思惟の間に、詞や音が、すとん、と腑に落ちるような瞬間がある。こんなことにも気が付かないまま聴き続けていたのか、ということもある。同時代の歌ですらそうなのだから、和歌や謡曲となると、そのわからなさにいよいよ途方に暮れる。それでも聴くのは何故か。
記憶を語ることもまた、似ている。ただ起きたことを筋道立てて叙述していくだけでは、何かが足りない。古井由吉『白暗淵』の文庫の解説に引用された、氏の言葉が目についた。
「若い頃に、ムージルを翻訳していましたとき、そんなに読み込めるわけじゃないんですよ、あの年からしてね。そうして難解な本でしょう。意味を外すまいとして意味の方に神経が行く。するとね、意味のことばっかり考えて、読んでるうちはいいけど、日本語に訳すときに、何か間違えが出るんですよ。意味っていうのは、はたして論理だけに運ばれてくるものか。音律にも運ばれてるんじゃないか。これ、日本語に訳すっていうのは、もう一度歌い直すようなもんでしょう。これに乗るか乗らないか。これで苦労しすぎて、とうとう学問の道からそれてしまったんだと思いますけど。」
「それから、リルケを訳したときにも、作家と言っても、もう近代になってからは、決して自分で声に出して読むようには書いていませんね。それは近代の一つの必然的な傾向では、あろう。だけど、文学ってもっと広くとった場合ね、歌謡、歌ですか。歌謡とも強く結びついてる。
すると、そういう伝統から別れなくてはならない、論理の方に行くとね。それは精神的な覚悟としてはよろしいんだけど、そのとき言葉に力がなくなるんじゃないか。言葉に歴史的にこもった力。これ、自分一個のもんじゃありませんよ。それに見棄てられるんじゃないか。」
膝を打った。ずっとわかっていたはずのことのような気がするが、焦慮の末に盲いられてしまう。そうして、歌とは、遅さだ、と思った。それは歌や詩であろうと、小説や随想であろうと変わらない。論理や説明は確かに早い、が、声を置き去りにしてしまうのではないか。否、置き去りにされてしまうのではないか、と。
『白暗淵』は古井氏曰く、「何とか意味に声が伴うようになってきた頃の作品」の一つだという。古井由吉は戦争の記憶を歌おうとする。執拗に。反復する。その不穏さを、ここに書かれている災禍を、いつのまにか忍び寄り日常を浸食していく何かを、私たちもまた生きているような気がしてきたところである。
「虚構とは始めが恣意であり、考えきれずに迷い出るようなものであり、やがて途方に暮れて茫然としたところで、紛れ失せた記憶を外から、見も知らずの人の、垣間見せた姿として、招き寄せるのではないかと考えた。それぞれに年を経て、それぞれの所で暮らしていても、探す記憶の、面影らしいものがまつわりついている。」
ー「年の坂」(著者から読者へ)より
下手な歌を諦めようとしたこともあるけれど、この背中を見てしまった。腹を決めるしかない。
 三嶋 佳祐
三嶋 佳祐
ゆだちというバンドで音楽活動、アルバム『夜の舟は白く折りたたまれて』を全国リリース。音楽、小説、美術など様々な制作活動で試行錯誤。書物、蒐集、散歩、アナログゲーム、野球を好む。広島カープのファン。
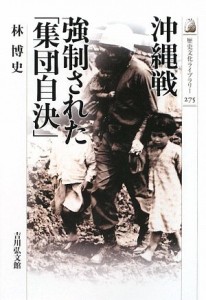
林 博史
『沖縄戦 強制された「集団自決」』
吉川弘文館2009 年
(手榴弾を爆発させたが不発も多かった後)突然、私の目に一つの異様な光景が飛び込んできました。一人の中年の男性が、一本の小木をへし折っているのです。私は、いぶかりながら目を凝らしました。男性はついに小木をへし折りました。そしてその小木が彼の手に握られるや否や、それは〝凶器〟へと変わったのです。彼は、自分の愛する妻子を狂ったように殴殺し始めました。この世で目撃したことのない、いや想像したことさえない惨劇が、私の眼前に出現したのです。以心伝心で、私ども住民は、愛する肉親に手を掛けていきました。地獄絵さながらの阿鼻叫喚が展開していったのです。剃刀や鎌で頸動脈や手首を切ったり、紐で首を締めたり、棍棒や石で頭部を叩くなど、戦慄すべきさまざまな方法が取られました。母親に手をかした時、私は悲痛のあまり号泣しました。私たちは「生き残る」ことが恐ろしかったのです。わが家は両親弟妹の四人が命を断ちました。
――金城重明さんの証言(当時16歳)
この証言のもとで、一つ銘記しておこう。わたしたちが忘れてはならないのは、わたしたちが過去の記憶に対する影響力を保持しているという避けがたい事実である。わたしたちは簡単に過去の記憶を歪め、忘れ去ることができる。翻ってみるならば、過去を正しく記憶し、未来へと紡いでいくことがこの上なく困難であるということだ。
本書にしたがい、本書が書かれる背景となった状況を簡単に確認しておこう。2007年に、わたしたちの歴史教科書から「集団自決が日本軍によって強制された」という文言が消し去られた。文部科学省が教科書検定において「強制」を認めなかったのである。この「強制」の削除に安倍内閣が関与している(安倍内閣で当時副官房長官に就任した下村博文議員は教科書への政治的介入を公言している)。安倍内閣とその取り巻きは、「集団自決」は「強制」ではなく、「自ら国家のために殉じた崇高な死」として描きたいのだ。また稲田朋美議員によれば「いざというときに祖国のために命をささげる覚悟がある」ことがエリートの条件なのだという。
この権力による忘却と歪曲に晒された記憶とはどのようなものか。本書によれば、日本軍が市民に集団自決をさせるために配っていた手榴弾では死に切れないことがあるため、家族においては父親が、両親や妻、そして子どもたちをあらゆる手段で手にかけねばならなかった。しかし例えば、棍棒で自分を殺すことは難しい。多くの場合、父親は生き残ってしまうという。そのような人たちは、どのような思いで戦後を生きたのだろうか。わたしは幾度となくその記憶に誘われ、ときには執拗にそのことばかりを想像してしまうのだが、起きた出来事の恐ろしさに絶句するほかない。
安倍内閣が日本を「美しい国」にするために消し去ろうとしているのは、単に過去に起きた「事実」だけではない。その過去の事実がもたらす記憶と、わたしたちがその記憶に触れ、それを想像し、絶句する場所そのものを消し去ろうとしているのである。もしも、その場所がなくなり、誰もが忘れてしまうのならば、その記憶は最初からなかったことになってしまうのではないか。そしてそれはどれほどのことなのか、計り知ることができない。わたしにとってそれは、死者を再び殺すようなものだと思われてならない。
過去をどのように記憶し、忘却するのか。それはつねにいまを生きるわたしたちに委ねられている。いかにありきたりで、困難なことであろうとも、わたしたちは過去の記憶から学び、それを未来へと繋いでいくことをやめてはならない。忘れ去られようとしている沈黙の中に声を聴きとるために、ぜひとも本書を手にとってほしい。それにしても、思い出されることを待っている記憶がまだどれあるだろう。わたしたちが何食わぬ顔で忘れ去って、そのままになっている記憶が。
 牛田悦正
牛田悦正
1992 生。Rapper。ヒップホップバンド「Bullsxxt」のMC。1st アルバム『BULLSXXT』を10/18 に発売予定。著書多数。

纐纈 厚
中央公論社1996 年
淡々とした歴史記述が続くが、現在の日本の政治状況と照らしてみればゾッとするだろう。保身のために戦争をずるずる引き延ばしたグループは、責任を陸軍になすりつけることで、なんの反省もなく戦後日本の支配層となり、それが現在まで続いている。これは過去の記憶と一続きになっている現実の悪夢だ。いま、そのツケを払う時がきている。
牛田悦正

ジョルジュ・ディディ= ユベルマン(橋本 一径⦆訳)
平凡社2006 年
アウシュビッツの絶望的状況の中で、ゾンダーコマンドのメンバーが残した4 枚のフィルムの切れ端、その断片的なイメージから、歴史を再構築せんとする果敢な試みの書である。出来事、現実という「すべて」に、想像不可能なものに抗って、どのように我々は歴史を、記憶を紐解いてゆくのか。想像することの不可能とは、一つの前提ではあるかもしれないが、結論ではない。私たちはここから、知ることを始めなくてはならない。
三嶋 佳祐

カルロ・ギンズブルグ(上村 忠男 訳)
みすず書房 2003 年
歴史の叙述とはどのようにして可能なのか。証拠を全て鵜呑みにするわけでもなく、また証拠を全て無視をするわけでもなく、史料への批判的分析を経た上で歴史を叙述せよ、という、あまりにも真っ当な主張がなされる。しかし、この真っ当さというのは、現代においては忘れられがちなことのようである。歴史修正主義者が跋扈し、両論併記すべきでない主張を併記するメディアが溢れるなか、とかく「私の思い」に傾きがちな寝惚けた人々に一撃蹴りをくれてやるのには絶好の書である。
三嶋 佳祐
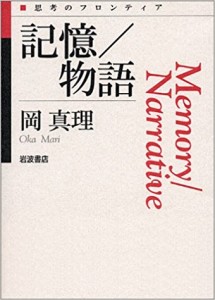
岡 真里
岩波書店 2000 年
著者はアラブ文学研究の岡真里先生。記憶とは物語ることによってしか紡がれない。記憶と記録は別のものである。物語ることによって記憶される記憶はわたしたちにとって、どのような意味を持つのか。リアリズムの手法によって再現不可能な出来事をあたかも再現出来るかのように描くハリウッド映画に抗して、その出来事の語り得なさそれ自体を描く可能性を文学に見る。そもそも小説とは国家との関係で阻害された生の経験を物語る役割を引き受けてきたのではないかという古典的な問題を、世界中の作品を分析しながら現代的な視点から極めて明確に整理していく入門書である。それにしても、入門書らしからぬ熱のある文章で綴られたこの書物は、研究者のみならず、記憶や文学に関心のある全ての人に開かれたバイブルにもなっている。
三浦 翔
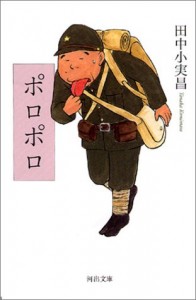
田中 小実昌
河出文庫 2004 年
表題作である「ポロポロ」の他は中国戦線で経験した従軍生活を著者独自の文体で綴る連作となっている。そう聞くと身構えてしまうだろうが、実際に読んでみると肩透かしを食う。もちろん過酷には違いないが、その語りは飄々としていて、どこか滑稽にも思える。おそらく書き手としてもそれが狙いではあるのだろう。それらの話を読むと、自分がある種の「戦争にまつわる物語」をどこかで期待していたことに気づかされる。だが書き手はそうした物語になることを拒否する。あたかも生理的にだ。物語は語ることができる。しかしそのことによって何かがこぼれ落ちる。記憶とは本人にでさえも不確かなものなのだ。だから書き手はそのことを隠さない。そのためこの連作は神経質なほど記憶に忠実であろうとする。つまり描かれているのは極めて個人的なものであり、そしてそのことこそがこれらをすぐれた戦争文学たらしめている。
小林 卓哉

集英社 2011 年
「コレクション戦争と文学」は、集英社創業85 周年を記念して企画された戦争にまつわる文学を巻ごとに編集したシリーズであり、全20 巻+別巻1 冊のいわゆる「文学全集」である。年代別にしたものや、広島や沖縄などの地域別に編んだもの、ある特別な語りをする作品を集めたものなど、豊富なテーマがある。収録されている作品の幅も広く、明治期の作家や詩人、現代の作家など、ジャンルや年代を問わない。また、こういったアンソロジーの一番の魅力はそれまでは知ることのなかった作品に出会うことだろう。本巻も多数の作品が収録されており、そのどれもが新たに目を開く契機となるようなものになっている。シリーズすべてに目を通すことはおそらく困難だが、自分の関心と響きあうテーマのものを一冊手にとってみることは個々の小説を通して戦争について考える一助となるに違いない。
小林 卓哉

野家 啓一
岩波現代文庫 2005 年
著者は哲学者の野家啓一。物語とはなにか、言葉とはなにか、現象学をはじめ様々な哲学を使いながら民俗学者柳田國男の口承文芸論を掘り進めていくことで、物語が複数の読み手によって読まれることで編み出す共同性を明らかにしていく。歴史とはしばしば物語の集合であると言われるが、そうした大きな物語=歴史が冷戦後の世界で不可能になった(歴史の終焉論)ということが刊行当時は盛んに議論されていた。大きな歴史が不可能になったあとどのように物語=歴史は可能なのかを問うたこの書物が、3.11以後に様々な意味で分断が叫ばれる日本社会に再び読まれるべき論点はたくさんあるであろう。とくに、その場で相手に向かってメッセージを「話す」ことと経験を反復されるかたちで「語る」ことの違いを考察した二章の議論は示唆に富んでいる。
三浦 翔

PUNPEE
Album『MODERN TIMES』より2017 年
実は昔Hero はこの世に実際居てでも色々あってどこかに消えた僕らは記憶を消され かすかな記憶達がコミックになり残ったこの曲は唯一それを覚えてたPUNPEE から君に送るメッセージさ偉い人に化けた異星人が想像力を惰性で流そうと目論んでる! ってまた。。。あの芸術家たちもあの戦争に行ってたら死んでたかもあの戦争の犠牲者の中にも未来の芸術家が何人居たろう?きっと彼らのアイディアは空気を伝って僕らが形にしてるこぼさずに灰色の世界にひらめきを夢のような暇つぶしをつくりだそうぜ Hero
三嶋 佳祐
 三浦 翔
三浦 翔
1992 年生。大学院生。監督作『人間のために』が第38 回ぴあフィルムフェスティバルに入選、現在「青山シアター」にて配信中。理論研究と作品制作を往復しながら、芸術と政治の関係を組み替える方法を探究している。