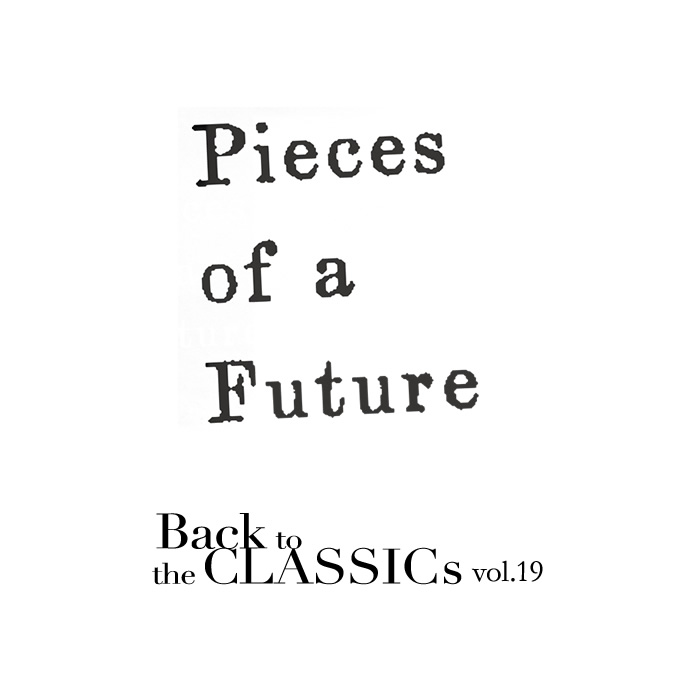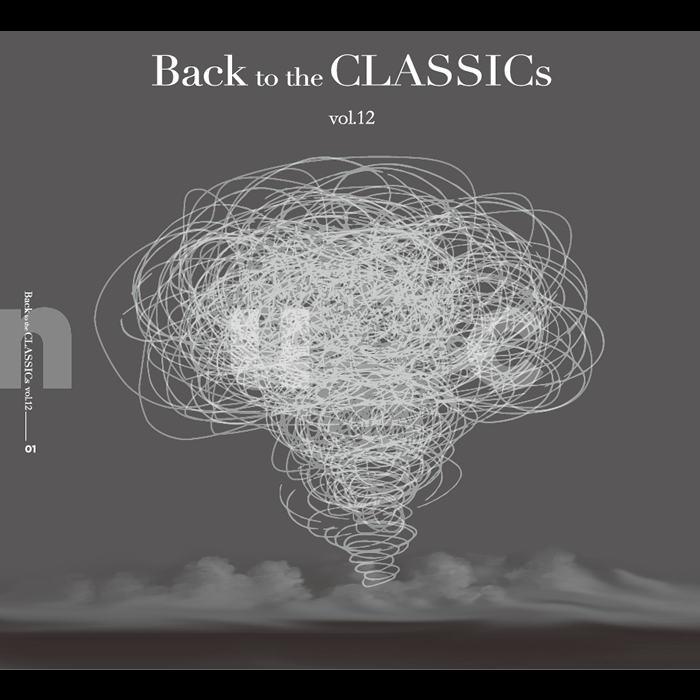Back to the CLASSICs vol.07 “ I don’t know what love is. ”
『愛することを学ばなければならない』
音楽に聴き入るとき、われわれの内部に生じること、—まずはとりあえず主題と曲調を聴くこと、つまり聴き出し、聴き分け、それ自体として独立した生命をもつものとして分離・限定することを学ばねばならない。続いて、たとえ馴染みがなくても、それに付き合うだけの労力と善意をもち、その眼差しや表情をじっくりと眺め、奇矯な点をも大目に見なければならない。 —そうすれば、やがてはわれわれが音楽に慣れてしまう瞬間がやってくる。音楽を期待し、音楽がなくてはいられなくなるだろうと予感する瞬間が。そうなると音楽はさらにとどまることなく威力と魅力を発揮し続け、ついにわれわれはその献身的で心酔した愛人となり、もはやこの世にそれ以上のものを求めず、ひたすら音楽だけを願うようになるのだ。 —しかしこれは何も音楽に限った話ではない。いまわれわれが愛しているものすべてについても、ちょうど同じようにして、われわれは愛することを学んだのだ。疎遠なものに対して、善意と忍耐をもって公平に優しく接すれば、それは最後にはかならず報われる。そうなると、疎遠なものも徐々にその覆いを脱ぎ捨て、言い尽くしがたい新しい美として現れてくるからである。 —それはわれわれの歓待に対する感謝である。自分自身を愛している者も、同じやり方でそれを学んだのだ。それ以外の道は考えられない。愛することもまた、学ばなければならない。
(フリードリヒ・ニーチェ『喜ばしき知恵』(村井則夫訳)河出書房新社)
触れてみる前はなんでもなかったものが、一度その面白さに気づいてしまうと手放せないということはよくある。しかしすごいものはなんでも触れ続けてみないと、その面白さに気づくことはできない。面白いものに出会うためには忍耐や努力が必要なのだ。
高校生のとき、まだ「日本語ラップ」を少し聴く程度だったころ、本場のヒップホップを聴いてみたいと思い、5000円片手に、新宿のディスクユニオンのヒップホップ館に行き、店員のお兄さんに「これだけは聴いておかないとまずいでしょ、みたいな洋楽のヒップホップのアルバムを3〜4枚選んでください、それを買います」と言うと、お兄さんは苦い顔をしながら選んでくれた。
1枚目はSugarhill Gangの”The Best Of SugarHill Gang”で、これはブレイクダンスをやっていて”Apache”とかは知ってたし、初めて流行ったラップのアルバムだけにとてもキャッチーだったので割とすんなり聴けたけど、その分すぐに飽きてしまった。
2枚目はGang Starrのデビューアルバム”No More Mr. Nice Guy”だった。確かにDJ プレミアのビートは「これぞヒップホップ」って感じだし、聴かないといけないけど、今思えばよりによってデビューアルバムにしたのは店員さんの悪意なのか、それともすごく渋かったのか。なにせこのデビューアルバムはかなり荒削りに聞こえるし、ちょっと聴いてみてもつまらない。みなさんも少し聴いてみてほしい。ヒップホップに興味を持ちはじめたピチピチ高校生がこれを聴いてヒップホップにハマるのだろうか!
幸い、僕はこれを聴いて完全にハマってしまった。最初は本当につまらないし、もしかして店員に騙されたのか?とすら思ったが、それでもお金がもったいないので毎日ひたすら聴き続けたら、単調なジャズサンプリングのループがどんどん心地よくなってきて、中毒みたいになってしまった。3枚目のGroup Home”Livin’ Proof”も、同じくDJ プレミアがプロデュースしたものでいまだに手放せない。
問題は4枚目、JayDeeの”Welcome 2 Detroit”だ。これはなかなかキツかった。Gang StarrとかGroup Homeと同じ頻度で聞いていたけど、あまりに何も起こらないので、聴くのをやめてしまった。
そのすごさに気づいたのは大学生になってからだった。大学生でジャズ研に所属(といってもほとんどスタジオの近くでスケボーしてただけなんだけど)していた僕は、友達とよくグルーヴだのノリだのの話をしていた。ヒップホップっぽいノリでオシャレなロバートグラスパーとか、ディアンジェロとかを聴いて、3拍目のスネアがヨレてるけど、これは後乗りだ、いや逆にグルーヴってのはそもそも全体で一瞬走ることだ、とかいろいろ言ってたんだけど、その時にそういうヒップホップっぽいノリの音楽をやってる人の多くはジェイ・ディラって人から影響を受けているらしいことを知った。ジェイ・ディラってなんとなく聞いたことがあって、そういや大好きなATCQとかデ・ラ・ソウルとかのトラック作ってる人じゃんってわかったときからもうジェイ・ディラのビートがすごい好きになってずっと聴いていた。あるときふと、ジェイ・ディラのことをネットで調べていたら、高校の時に買った覚えのあるCDのジャケを見つけた。その直後からだった。ノリとかグルーヴのようなものを少しは体感的にわかるようになってきた僕が”Welcome 2 Detroit”をこよなく愛するようになったのは。あの時、全く面白くないと思って聴いていたJay Deeはジェイ・ディラのことだったのだ! なんて最高な再会だったか、それは僕にしかわからないだろう。昔つまらなかったものが、こんなにも素晴らしく姿を変えて目の前に現れるなんて想像もしてみなかった。
それから僕は目の前にあるどんな音楽に対しても敬意と歓待を忘れずにいようと思った。というのも、音楽は必ずと言っていいほどに僕たちの敬意と歓待に答えてその汲み尽くし難いほどの豊かさを与えてくれるからである。そしてなにもこれは音楽に限ったことではない。愛することを学ぶとは、確かにある種の忍耐を要するものであるだろう。しかし、その道中は——いや、まさに愛することは常に道中なのだが——想像もしてみなかったような喜びで満ちているのだ。
 writer:牛田悦正
writer:牛田悦正
1992生/ラッパー
『個人的』
1.「愛」とは、基本的に非常に個人的なものだと思う。ある一定のものに対する愛情を100人の人が抱いたとき、その愛情の形は100通りあるし、他人の抱いている愛情の形を100%理解する事は、きっと不可能だ。日々の生活の中でも、自分のこの「愛」はきっと誰にも理解できないだろうと感じることが多々ある。そういう時の僕は、周りからの理解を期待していない部分もあるし、同時に理解を拒否している部分もある。きっと、そうすることで、その「愛」をより研ぎすまし、さらに尊いものにしようとしているのだろう。
「愛とは個人的なものである」もしかしたら、誰しもが分かっていることかもしれないです。
2.一人で電車に乗っている時、全く興味のない大学の授業を受けているとき、どうでもいいバンドのライブを見ているとき。そういうときに時々「音楽の最小単位って何だろう」と考える。リズムやメロディなどが存在しない無調の音楽なんて沢山あるし、そもそも音が鳴っていなくたって、それを音楽だといってしまえば音楽になるだろう、実際にそういう例もある。
こんな具合に考えを張り巡らせても、大体結論は出ない。なので最近はもっと範囲を縮めて「ポップス、歌がある音楽の最小単位とは何だろう?」と考えていた。答えはものすごく簡単に出た。ぼくは「歌と、最低限の伴奏」をポップス、歌ものの最小単位だと一応結論づけた。「最低限の伴奏」というものは人それぞれ違う解釈が存在すると思うけど、ぼくがぱっと思いついたものは、ギターやピアノでの伴奏だった。
今まで色んなジャンルの音楽を見たり聞いたりしてきた。もちろんまだまだ聞いてないものや未知のものも沢山あるけど、やっぱり自分が一番好きなものは「歌の最小単位」という概念を感じられるものだなと思う。そして、それの代表的なものはやっぱり「フォークソング」だ。
普段所属しているバンドで爆音を鳴らしているJ mascisやJames Ihaや山本精一のソロアルバムが、かなりフォーク寄りなのも面白いなと感じる。それはもちろん彼らの奥底の部分にフォークソング的なものに対する愛情があるからだと思うし、何より、フォークとかそういう類いの音楽は、一人で作るからこそ輝く、非常に個人的な音楽なのかなと感じる。
ぼくはそういった彼らの好き勝手やっている個人的な感じも含めて「歌の最小単位」感のあるものがとても好きだなあと日々感じている。
朝起きて、顔を洗って、朝食を食べるなりして、部屋にあるギターやピアノをぽろぽろと弾くうちにメロディが浮かんできて、MTRやレコーダーで何となく録音して、、、、、。そういう雰囲気や空気を何となく感じられる音楽を聞いていると、幸福な感じもするし、切ない感じもするし、なんとも言い表せない感情になってくる。何故そんな感情になるかと考えると、やはりそういった個人的な音楽には、なにかその曲を慈しむような、作者の非常にパーソナルな愛情を感じるからだろう。バンドやグループで音楽を作るときは、セッションで作る場合でも、誰かが曲を持ってくる場合でも、まず「共有」という段階を踏まなければならない。対して一人で作る音楽は最初から最後までずっと一人。
一人で作ったものというのは、その曲を作る中で生じるであろう、様々な感情を何一つ共有しないまま、完成に向かっていく。そうして出来た作品には、やはりなにか特別な雰囲気がある。
3.今回は三曲を選曲しました。作曲した彼らの頭の中を、少し覗くような感じで聞いてみて下さい。
戸張大輔 / 無題5
彼のプロフィールに関してはネットで調べて見て下さい。とても面白いので。戸張大輔の好きなところは、やはりメロディが非常にポップなところ。何と無く懐かしい感じがするのだけど、かなり強烈なメロディだと思う。あとは、歌詞がやたらキャッチーなところも不思議で格好いい。「マジで楽しんでくれ、心踊らせて」なんて歌詞、なかなか書けない。
Todd rundgren / wailing wall
Todd rundgrenはポップス史に残る、最高のアレンジャーだと思う。突拍子もないコーラスとか、リズムの変化とか、とても魅力的。でもこの曲に関しては特にアレンジは施されていない。ピアノ弾き語りに味付け程度のコーラスといった感じ。そしてこの曲はとにかく丁寧に歌われている。Todd rundgrenの歌声って少しぶっきらぼうと言うか、そういうところも格好いいのだけれど、この曲に関しては一音一音噛みしめるように丁寧に歌っている。それが、とても切なくて、でも救いがある感じが少しして、好きです。
Nick drake / place to be
3rd albumの「pink moon」に収録。全編弾き語りのアルバムで、プロデューサーからの「アレンジはどういう感じにする?」という質問にNick drakeは「アレンジはいらない。これ(弾き語りだけの状態)で完成なんだ」と言ったのは有名な話。作曲者の内面がそのまま出ている一曲だと思う。でもそれはとても痛々しくて繊細な感じがする。名曲だと思います。
 writer:加藤寛之
writer:加藤寛之
趣味は楽器を演奏すること。
毎回、一定のテーマで何曲か選曲していこうと思います。
『素晴らしい』
ロラン・バルトが書いた本のうちに『恋愛のディスクール・断章』という、装丁が美しくてつい手にとってしまいたくなるような本がある。表紙の四辺がうすいピンクで縁取られていて、中央には、明らかに元の絵画からトリミングされてある、二人の人物の手がなんとも言えない具合に触れ合っている絵画が置かれている。元の絵画は一体どういうものなのかと思って調べてみると、ヴェロッキオというルネサンス期の画家の『トピアスと天使』という作品らしくて、トピアスという名の少年が天使について歩いているところが描かれている。
それは一見、少年が天使に手を引かれて歩いているように見えるけれど、二人の手はなんとも言えない具合に触れ合っているだけで、天使は実際に手を引いているわけじゃない。正確に言おうとするなら、天使が自分のスカートを手繰りあげている手の内側からトピアスが手を通し、そのまま天使の手首をつかもうとしているように見える。
それでちょうどその手の部分だけがトリミングされてこの『恋愛のディスクール・断章』の表紙になっているわけだけど、これはバルトにぴったりだと思う。バルトの本をいくつか読んでみるとバルトが何を楽しもうとしている人なのかが分かってきて、その点でこの絵の「微妙」な感じというのはとてもバルト的だ、という気がしてくる。
内容の方はどうなのかというと、タイトルにある通り恋愛に関する雑感だったり考察だったりがフランス人お得意の(?)「A to Z」に準じながら断章形式で書かれている。断章のそれぞれには連関が有って無いようなものだから、どこから読んでもいいというのが心地いい。
フィギュール群が整理されえぬこと、順位もなければ筋道もなく、なにかの目的(制度)に向けて力を合わせることもないというのが、このディスクール(ならびにそれを表すテクスト)の原理にほかならない。P.12
恋愛に関するあれこれなわけだから、やっぱり読んでいる間は具体的な人の顔を頭に思い浮かべることになるのだけど、そうして誰かを思っている自分と、同じように誰かを思っているバルトが恋愛の中で一喜一憂しながら書きつけたテクストが共振するとき、同時に、それとは裏腹に、恋愛の状態を表す言葉の不的確さも露わになってくる。かといってJ-POPみたいに「言葉じゃ表せないこの想い」なんていうのは誰でも思いつくことで、だけど「言葉じゃ表せないこの想い」という表現はすでに形骸化していて、だからここでは「言葉じゃ表せないこの想い」の存在それ自体はその言葉では捉えられていない。
バルトの嫌がるもののひとつに「ステレオタイプ」ということがあって、それは、言語化するのにかなり苦労するような複雑で豊かな心の有り様は確かに存在しているのに、それを言い表すときの言葉が使い古されていると、その心の有り様も急に判を押したようなつまらないものとなってしまう、というようなことだ。この意味で、言葉は裏切りを含んでいると言える。
この裏切りに対してこちらが取れる身ぶりとしては、諦めて口を閉じるか格闘するかがその大体で、恋愛の場で無口になるという選択もできないことはないけれど、そういうとき、人は饒舌になりやすい。それというのも次々と口から繰り出す言葉が言うべき「それ」を捉え損ねているからで、手数を増やしてみても状況はおそらく一向に変わらない。
そうして、この苦闘の行く末は「素晴らしい(あるいはそれに準じるなんとも単純な)」の一語にたどり着くことになる。
欲望の的確さは言表の不的確さしか生みだせない。こうした言語の失敗のあとには、ただひとつの痕跡しか残らないのであり、それが「素晴らしい」という語なのだ(略)。P.34
この「素晴らしい」というのは、言葉を尽くすのに疲れきった上で出てきた残滓のような一言に他ならない。だから、「素晴らしい」というのも具体的にどこがどうという話じゃない。どこがどう素晴らしいのかを言いあぐねるからこその「素晴らしい」なのであって、つまり、あらかじめこの語は挫折している。ここに行き着いたときに残されていることといえば、その同語反復を認めること、ただそれを繰り返すことだけになる。「素晴らしいものは素晴らしい」。
この反復。一見投げやりのようにも思えるこの反復は、「素晴らしい」という語をまさしく同じ語で肯定する。それはいわば、自分の欲望を丸ごと肯定することであって、心は、言語化することのできないフラストレーションを抱えつつもそれ自身で充足はする。ふと、ここで、ある経験から、ひとつの疑問が浮かぶ。「しかしこの言語活動の失敗は、むしろそのことによって情動の全体を余すことなく伝播させることがあるのではないか?」。
ひとつのコミュニケーションの形を思い浮かべてみる。互いに使う言葉は少なく、それによって仔細なことが伝わるとは到底思えないけど、それでいて二人は奇妙に充足している……。
ロラン・バルト『恋愛のディスクール・断章』三好郁朗訳 みすず書房
 writer:小林 卓哉
writer:小林 卓哉
1992年生まれ。大学在学中、保坂和志とロラン・バルトに感銘を受け文学に強い興味を抱く。
現在都内で販売員をする傍ら執筆中。
『人はつねに愛するものについて語りそこなう』
一時期、届いた郵便や手紙に書かれた手書きの文字を一字ずつ切り取って瓶に入れていた。ご時世、手書きの文が送られてくることは少なくて、瓶の底が見えなくもならないうちに(結果的に三日坊主みたいな状態で)瓶に埃が被り始めてしまったが、それに「言葉の破片」という名を付けている。 ロラン・バルトの、邦訳では『テクストの出口』という書物の中の「F・B」という、結局作品を発表していない作家の断章の余白に書かれたらしいテクストの中で見た言葉だった。
読むことが叶わない断章について書かれたテクストを読むということに少しロマネスクな欲望を擽られながら頁を捲ると“スタンダールはすでにシャトーブリアンを嘲笑し、ほとんどまったく推敲しなかった”という一文に衝突して、それが気になってスタンダールの小説も買ったけれどそれはまだ読んでいない。
そんな風に書き出してみたこの文章はバルトの書評を書こうとして始めたのだが、結局二万字くらい色々書いては消している。今はまだバルトのことを書けない気がしてきた。私は「読めていなさすぎる」のではないか、という思いが募るばかりだ。
同書にはスタンダールについてのテクストが別に収録されていて、「人はつねに愛するものについて語りそこなう」と題されたそれはバルトの遺稿でもある。これはスタンダールの言葉らしい、大岡昇平も引用していてそれが遺稿になったという。(私はまだ死にたくないけど。)
書くことは茫漠とした海市をただ眺めるに終わるかもしれない。「答えが出ないことを考え続けるのは無駄じゃないか」と言う人がいる。そういう功利的な考えを今持っている人には伝わらないかもしれないけれど、考えるとか本を読むとか書くというのはこの矛盾を生きることでもある。
作品を作ることや人と対話することもそうだろう。常に病うことになる不在への眼差しと、不可能性を生きることが「愛する」という行為なのではないかと、月並みだが今のところは考えている。明日はわからない。
だから読むことや書くことは当然に苦しい。一冊の本の文字数や体重や売上は数字にできるだろうけれど、それがなんだというのだろう、言葉たちの宙を漂う書物の外には書物にならなかった言葉もある。書物は砕かれた星達の途方もない遍歴、散り散りの過去の光が交錯する庭だ。
毎日何かしらの本を開き、「読めなさ」にぶち当たって朝まで考え込んでしまっても、そのせいでその日のバイトが眠くて辛くても、繰り返し読もうとし、書こうとする。書きたいと思う。なぜか?わからない。
これはもう症候なのか。書物という贈与への返礼としての。
バルト(に限らずだが)を「読めた」と思えたことは未だない。しかしどんな本にせよ「読める」ことなんてあるのだろうか、「読めた」と思ったとしても、それは傲慢の罠なんじゃないか、そもそも「正しい読み」なんてあるのだろうか、そんなものはないというのはその通りだと思うし、バルトもそう言うかもしれない、ただ例えば「作者の死」を援用して「どんな読みも正解だ」と開き直るような態度は違うんじゃないか、バルトはそんなことは言っていないんじゃないか、彼もまた書くことの不可能性に苛まれ、その中でこそ書こうとしていたのなら。
「正しい読み」がなくとも「誠実な読み」というか、少なくとも書かれたものに対して「誠実であろうとする読み」、時間をかけて、いわば苦楽を追体験するように読む、少しでもその呼吸に近付こうとする読み方をやはり志すべきじゃないだろうか。できていない私が言うのもおかしいかもしれないけれど。
バルトは小説を書きたいと言いながらその生涯で結局書かなかった、と言われる。私は安易に「これを小説と呼んではいけないのか?」と思う。でも大事なのは、バルトが「小説と呼ば(べ)なかった」ことの方なんじゃないか。それを考えることと「解釈しない」ことは矛盾しないんじゃないか。いや、そんなこと以前に、私はいつも書物を「当然のことのように」読んできた。とりあえずそのことは忘れない方がいいような気がする。
“イタリアへの愛を語ってはいるが、それを伝えてくれないこれらの「日記」(これは少なくとも私自身の読後感ですが)だけを読んでいると、悲しげに(あるいは、深刻そうに)人はつねに愛するものについて語りそこなうと繰り返すのももっともだと思うでしょう。しかし、二十年後、これも愛のねじれた論理の一部である一種の事後作用により、スタンダールはイタリアについてすばらしい文章を書きます。それは、私的日記が語ってはいたが、伝えてはくれなかったこの喜び、あの輝きでもあって、読者である私(私だけではないと思いますが)を熱狂させます。”—「人はつねに愛するものについて語りそこなう」
少なくとも私は勇気付けられたし、読むことと書くことを続けようと思う。
ロラン・バルト『テクストの出口』沢崎浩平訳 みすず書房
 writer:三嶋 佳祐
writer:三嶋 佳祐
1990年生まれ。自己紹介が苦手です。
Twitter:@fuku6fuku6
<Interview:ジョン・カサヴェテス Love Streams.1984>
“人々にとって「哲学」(Philosophy)とは、何なのでしょう。僕が思うには、「哲学」とは愛のことであり、愛を学ぶことだと思います。
ギリシャでは、“Phylos”とは、「友情」と、「愛」を意味していました。この二つは同義語なんです。一方、“Sophos”とは「何かを学ぶこと」ですから、「哲学」=Philo-sophyとはまさに「愛について学ぶこと」です。そういうことで、哲学を持つということは、どうやって愛するかを知ることになるでしょう。そして、その愛をどこに注げば良いのかを、知ること。そうして、友情、愛することの大切さを知り、それを持続させることがどれほど大事なのかを学ぶことです。
僕は、人は哲学なしで生きられるとは思いません。どこであなたは愛することが出来るのだろうか?愛を注ぐことのできる大切な場所はどこだろうか?というのも、愛は、どこにでも注げるものじゃないからです。歩き回っていて、「そうだ、私の息子よ」とか、「そうだ、私の息子よ、君を祝福する」と言うのには、聖職者が司祭になる必要があります。でも、人々はそんなふうに生きてはいない。怒りや、敵意や悩み、お金がないこと、何かの欠乏を抱えて、やりきれないほどの失望がある人生というものの中で生きている。だからこそ、人々が必要とするのは哲学、つまり「愛について学ぶこと」なんです。
その意味で僕は、誰もがこう問いかける必要があると思っている。「どこで、どうやって『愛すること』が出来るのだろう?『生きること』を可能とするために、少しばかり平和に生きていくために、『愛する』ということが?」、と。
きっと僕らが撮ってきたどの映画も、ある意味で、登場人物たちにとっての「哲学」、愛について学ぶことを、見出そうとしていたんじゃないかと思う。
だから、僕は愛を分析し、愛を議論し、愛を殺し、愛を破壊し、互いに傷つけあい、そうしたこと全部をするために、本当に登場人物たちを必要としている。—その戦いの中で。つまり「人生とは何か」ということについて、言い争われる言葉と、争いの絶えないような映像の中で。
それ以外のことは僕には全く興味がない。他の人々は興味があるかもしれないけど、僕の頭は一つのことしか考えられない。僕が興味を持つすべてのもの、それは「愛」だけです。それとその欠如について。愛が止まる時、本当に必要としているものが奪われることや、失ってしまうことについての痛みについて。だから、『ラヴ・ストリームス』はきっと、聖杯のようにどこかにあるかもしれない何かを探し求めることについての、一つの映画です。 ”
ジョン・カサヴェテス
1984年、映画Love Streamsについてのインタビューより。
 John Cassavetes
John Cassavetes
映画監督 1929年-1989年。
参考
Raymond Carney,Cassavetes on Cassavetes,2001. pp496.
『ジョン・カサヴェテスは語る』(ビターズ・エンド発行、幻冬舎.2000.)
「ラヴ・ストリームス」パンフレット(シネセゾン)
I’m Almost Not Crazy: John Cassavetes – the Man and His Work (1984)
4:00~ https://www.youtube.com/watch?v=NbvP8JNZZ8U
訳、引用 神宮司博基
どんな歳月にも堪えうるどころか、年を重ねるごとにその新たな魅力を発揮し、暗い未来をいつまでも明るく照らし続けてくれる、そんな「クラシック」を共に探求しませんか?