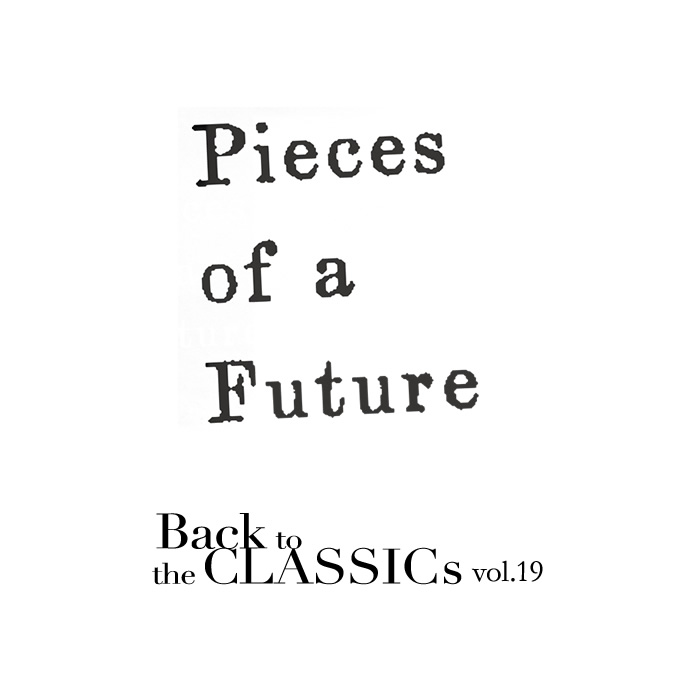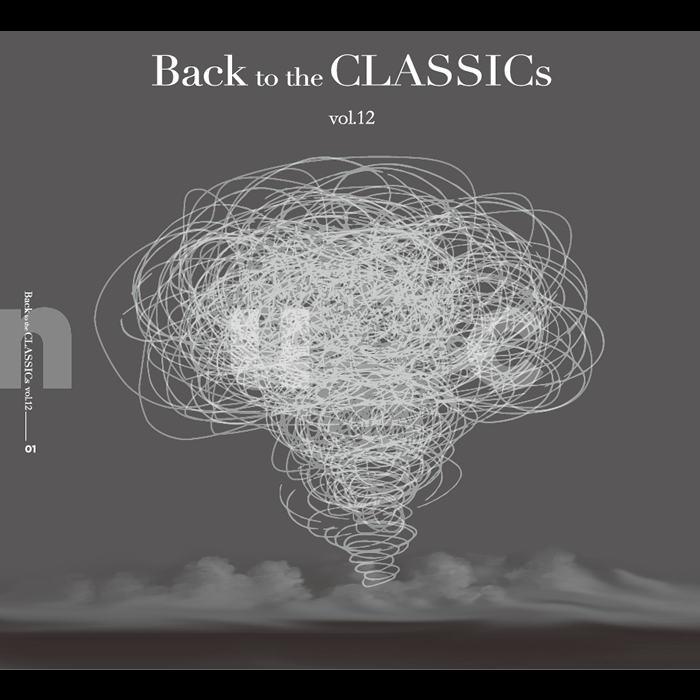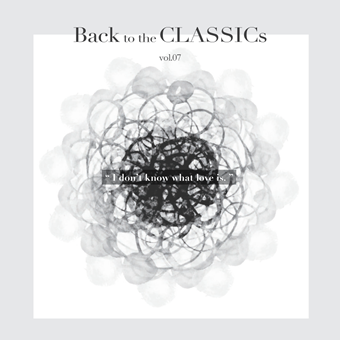Back to the CLASSICs vol.08
グルマンディーズ!
皆さん、最近御馳走食べましたか? 御馳走って、一体何なんでしょう? 卓に並べられた料理の数々を見て「わあ、御馳走だ」と思いますか? 正直に言うと、俺はここ最近まで御馳走という言葉が頭からすっぽり抜けてました。たとえうまそうな食べ物を前にしてもとりあえず「うまそうだ」と思うだけで、別に「御馳走だ」とは思わないんです。小さい頃は焼肉が御馳走だったように思います。駅前の牛角に家族と行って、本当に「これは御馳走だ」と思ってバクバク食べたのを思い出します。そんな牛角も今では居酒屋選びに困った時の最終的な候補地の一つです。焼肉は今でも好きですが、いつしか御馳走ではなくなってしまいました。
そんな俺が再び「御馳走」なんて言葉を思い出したのはサヴァラン先生の『美味礼賛』を読んだからなんです。「どんなものを食べているか言ってみたまえ。君がどんな人であるかを言いあててみせよう。」なんて超有名なアフォリスムがありますけど、この本のトーンは大体こんな感じで、覚えてる限りでも「読者は私に感謝しなければならない」場面が三回くらいあってびっくりしちゃいますし、基本は薀蓄だとは思います。けれどやはり食通で博識なだけあって料理に関する表現はなかなか光っていて、食いたいと思わせるのはさすがとしか言いようがない。特に肉に関する記述がいいんです。それにしても、特にヨーロッパの小説なんかに頻出する表現だと思うんですが「滋味溢れる」とか「滋味豊か」とかってめちゃくちゃうまそうじゃないですか。何というか、「食べたものは、そのまま生命に繋がるのだなあ」って実感できそうな表現ですよね。栄養が満ち溢れてると言いますか。「滋味豊かなスープ」とか超うまそう。あと「ぶどう酒」。ヘッセとかにやたら出てきたような気がする。やっぱり「ワイン」じゃ全然ダメで、というのもやっぱりそれは「果実感」がないからですかね。俺はビール二杯で頭痛がしてくる下戸なんですけど、ぶどう酒ならガンガンイケそうな気がする。「上等なぶどう酒」とかすごくいいですね。
この本が書かれたのは18 世紀の前半だそうで、サヴァラン先生の記述を読む限りではこの頃というのは科学的な実証主義がちょうど根づき始めた頃なのでしょうか。人体を解剖学的な観点から見ていたりして、結構驚きがあります。ただし「霊魂」といった表現なんかがちょこちょこ出てくるので現代から見るとちょっと眉唾感ありますけど。ただ馬鹿にできないのは肥満の原因は澱粉食にあると喝破して節制することを奨励したりと、これは今で言うところの糖質制限ダイエットなのでライザップに先立つこと約200 年。すごい。
だから、こういう現代にも通じるような基礎的な科学の知見もあれば、ちょっと軌道を逸れてしまったものもあるんだな、と大体話半分くらいに読むのが一番面白い気がします。
先生の文章を読んでいると、さて俺の食事はどうだったろうと思い返すことになりますが、ところがこれがあまりよろしくないように思います。月収20 万に満たない孤独な賃労働者が夜な夜なファミリーマートの前でチキンから溢れ出るジューシーな油脂で唇をテカらせて「うめーうめー」言いながらファミチキを食ってるのは傍目から見て結構マズい。ファミチキが不味いとかそういう話でなく(ファミチキは美味しい)、そういうものしか知らないというのがマズい。これは値段の張る高級な食材が買えないという単純に経済的な問題でもありますがそれ以上に、そのせいで自分が想像以上にものを味わうことができるのだということに気づく機会がないのが問題です。繊細で複雑な味を味わおうとすれば舌の力能はそれに応じて高まり、結果、より細かな味も感じ取れるようになるわけですから、それは豊かに味わえることに他ならず、つまり端的に言って喜びが増すということです。喜びが増すのならこんなにいいことはない。じゃあそのためにはどうしたらいいのか。
そこはやはり“グルマンディーズ”を志向するしかないでしょう!
グルマンディーズ(美食愛、うまいもの好き、食道楽)とは、特に味覚を喜ばすものを情熱的に理知的にまた常習的に愛する心である。p.195
なんと分かりやすい定義。ただしうまいものは総じてそれ相応の値段がつけられており、俺なんかはそこで足踏みしてしまうわけですが、しかしここでのポイントは「愛する心」である、ということでしょうか。このことは多分、うまい店を知ってるとか、高級食材を使うとか、そういうことを必ずしも意味してないはずです。少なくとも、直接には意味しない。大事なのは、食べ物にまっすぐ向かっていくような「美味しいものが食べたい!」という気持ち。いつも頬張るファミチキはレジで“ついでに”注文されたものではなかったか……。ないがしろにされたファミチキ……。これがいけない。そうではなく、自分を喜ばせるものだと思って食べ物を食べること。そして“グルマンディーズ”は、その「美味しいものを食べたい」という気持ちで人と人を結びつけ、一つの食卓を形作るのです。
結局、普通のところに辿り着いてしまったでしょうか。いやいや、しかしそれが失われた社会というのを想像してみると結構ディストピア然としてませんか。深夜の松屋、スマホ片手に牛丼を口に押し込む人々を見ているとこれは案外ポリティカルな話でもあるんだという気がしてきます。
ただ生命を明日に繋げるためにとりあえず何か食うのもいいけど、それは淋しい。そうでなく、生命を鼓舞するものとしてものを食べる、食卓を形成する、俺たち自身を喜ばす。皆さん、御馳走食べましょう。
ブリア- サヴァラン著 関根秀雄・戸部松実訳『美味礼讃 上・下〔全2 冊〕』岩波文庫
 writer:小林 卓哉
writer:小林 卓哉
1992年生まれ。大学在学中、保坂和志とロラン・バルトに感銘を受け文学に強い興味を抱く。
現在都内で販売員をする傍ら執筆中。
食べもののこれ性
美味しかったものがまるで美味しくなくなるということもよくある。昼過ぎには目覚め、目覚めの悪さと重い首痛で少し身悶えしながらそれでもうつ伏せのままパソコンを開いて小2 時間ほどYouTube を見ていたせいだろう。何もすることがないわけではないというか、やることが沢山で何から手をつけたらいいのやらわからず時間は過ぎて、ひとは腹が減る。やっとのことで冷蔵庫を開いて食べるものがないことを確認したら午後4 時で、夜からまた立てなおすと開き直ったら家を出る。あれはもう1 年目の春か、あるいは2年目の夏か、覚えはないが暑くはないからやはり春か。深く吸い込めば肌寒い夏には初冬の匂いが、暖かい冬には初夏の匂いがする、あの気持ちのいい風は1 年に10 回あるかないかでその日はその風が吹いていた。そういう日には決まってD’Angelo の2 枚目にある”The Root” を聴きチャリを漕ぐ。不思議な風を受けて懐かしくなっていたのか、いや想い出したわけではなかったと思うけれど、昔図書館だったものの向かいの、古いラーメン屋の前にいたことに気がついて自転車を止めて、そそくさと食べた。実はラーメン屋ではなく長崎ちゃんぽんのお店なのらしいがこの店でちゃんぽんを食べたのは数回で、だいたい注文するのはお決まりのラーメンと半チャーハンのセットだった。あの日以来もう二度と行かないと特に誓いを立てたわけではないけれどあのしょっぱいラーメンをもう一度食べようと思わなくてあれからもう3年は行っていないか。しょっちゅう食いに行ってお得意さんだったからここの店主はいつも50 円まけてくれる筈だったのに代わりに缶コーヒーをもらって胃が荒れたからではない。単純にもう美味しくないのだ。別になにかノスタルジックになっているわけではないが、ある特定の人間と食べなければ美味しくないものがあるというか、ある特定の人間とある特定の場所で、ある特定のものを食べた時にしか味わえないすこぶる美味いものがあって一つでも条件が欠けてしまえば台無しなのだ。そうであるならあれほど毎晩足繁く通った「ばってん軒」のラーメン半チャーハンセットは二度と美味しくなることはない。美味しい条件の一つであるあいつはもう帰らないから。「ばってん軒」における「あーこれなんだよ、これ」の「これ」はほとんど完全に失われてしまった。
失ったものは取り返しがきかないけれど、あれからも新しく美味しいものは沢山あっただろうし、いまもあるだろうし、これからもあるだろうではないか。それは失われなければ気がつかないのかもしれないし、気にしなくても気がついているのかもしれない。例えばもう帰らぬ人と帰らぬ「ばってん軒」の美味しさがある一方で、いま目の前にいる新しい人と食べるとんかつは特に美味しい。このとんかつが美味しいというよりも、この人と食べるこのとんかつやあのとんかつが美味しい。もちろんそれほど美味しくないこともないわけではないが。三太のとんかつは衣が特に荒く、食後にアイスが付いてくるのがいい。名前は忘れたけど六本木ヒルズの中にあるとんかつはスタンダードな感じなんだけど美味く、四ツ谷のとんかつはこの人を真似て塩をふるといい。だいたい舌が肥えているわけではないのだから、サクサクしててそこそこいい豚を使っているとんかつはだいたい美味いんだ。ご飯もお代わり自由だし、キャベツもお代わり自由だ(しかしところでこのお代わりの自由というのはいったいなんだ。お代わりをすればするほど周りの目や店員の目に晒されて不自由になる)。とはいってもこの美味しさはしかし、またしてもこの人との別れの後で「これ性が失われてしまえばなくなってしまうものなのか、それはまだわからない。だけどもとにかくときどき吹き抜ける不思議な風の匂いと同じで全てのなにかが完全にピタっとハマったときにだけ感じられるクワッとくる味のグルーヴが、とはいっても食べるものはなんであれかまわないのだけど、確かに存在するというのは他の人にたいして証明できないにしても、ともかく俺にとっては掛け替えなくあるんだ、ということだけ言っておきたい。
 writer:牛田悦正
writer:牛田悦正
1992生/ラッパー
焼肉と霞をめぐる独話
本を食べる友人Hは、その味のことを「罪の味だ」と形容していた。今これを読んで、本を食べるとはどういうことだろうと考えた人はいるかもしれないが、考えるようなことはない、文字通り食べたのである。といっても私はそれを見たわけじゃないし、家で食べるのだろうから、誰かを家に招いて食事していなければそれを見た者はいないだろうし証明の手立てはない。しかし私が敬愛している美術家の福田尚代の仕事のように、本に刺繍をしたり、穿孔したり、彫刻する人もいるのだし、本を食べる人間がいてもおかしくはないのではないか。(おかしいか。)
そもそも私たちは本を積む。私たちと言ったって今私の頭に具体的に誰さんや某さんが浮かんでいるわけではなく、私は「私たち」と言うことでこの記事を読む可能性を持つ人を含めた書物蒐集家の人々、本を積むことを生業の一つとしている人々の総体?というか全体(要は全ての愛書家か)について書いているわけだが、とにかく本を積むことだって同じようなものだ。そして時々それを並び替え(意図的にやることもあれば、気が付けば動いていることもある)、眺めて恍惚するではなかろうか。背表紙が見せる連関に思わぬ裂け目を見出すではないか。そして何より、読むではないか(これが本来の書物の使い道として普遍的に認識されている、なんて態々註を付けるまでもなく)。
つまり、Hが本を食べていると言った時も、私はそういう人を他に見たことも聞いたこともなかったが、笑いはしても別に嘘だとは思わなかった。いや、嘘かどうかなんてどうでもよかった。あらゆる言葉がフィクションでなかった時があっただろうか。何よりその話は面白かったし、「面白い」というのはその言葉を信じ込んでこその「面白い」だと思う。だから私はそれを本当のこととして聞いた。小説を読む時と同じように。まあ、後から思い出してもしかして冗談だったのかもしれない、と少しは思ったからこういうことを書いているわけではあるが、でもやっぱり本当だと思うし、そんなことはどっちでもいい。
私はHに「そういう芸として世の中に売り出していけば、食うのに困らないんじゃないの」と(冗談のつもりで)言った。Hは「断食芸人ならぬ本食(ほんじき)芸人ね」と言って、それにどう返していいかわからず苦笑いしたものだが、それがHとの現状最後の会話で、その後は疎遠になってしまったし、結局実際に本を食べているところは見たことがない。そういえばHが本以外のものを食べているところも見たことがない。随分痩せていたけれど、もしかすると他には何も食べていなかったのかもしれない。
カフカの断食芸人は死んでしまったが、Hはまだ生きている。といってもそんなに親しい仲だったわけではないから死んだという知らせがないからといって生きている証明にはならないのだが、知らせがない以上私の中では生きているし、そう信じている。信じているというか、「当然そうだ」と思っていて、「当然そうだ」と思っている状態のことを私は客観視?して「信じている」と書いている。
断食芸人は死んでしまった。バートルビーも死んでしまったけど、二人とも食べないで(食べることを拒んで)死んだ。食べなくて死ぬのは当たり前のことだと思うかもしれないが、日々食べるものが楽に手に入るということは実は当たり前のことではない。スーパーやお弁当屋さんに行けば食べるものはあるけれど、食材を作る人がいて、そこに運ぶ人がいて、調理して売ってくれるお店の人がいて、と多くの人の手を経て私たちはご飯を食べることができる。しかもお金がある場合に限ってだ。これは歴史の色んな場面、そして現在も世界の至る所の状況を見渡してみれば、決して当然のことではない。そして、食べ物が安定して供給されているからといって、断食芸人やバートルビーのような人がいなくなったわけでもない。
断食芸人とバートルビーの死の表情には些かの違いはあるかもしれない。それはとりあえず置いておくが、二人に共通していたのは変わらなかったことだ、変わりゆく時代や社会、周囲との齟齬故に、変わることができなかったために彼らは死んでいった。こういう人はカフカやメルヴィルの小説の中だけにいるわけじゃない。私たちの住む社会は常に侵犯とそれに「破壊された」人達の知られざる忍耐に満ち溢れている。(括弧内はブランショの言葉を借りた。)
ただ、私は断食芸人やバートルビーがそういう人々の形象であるとか象徴であるとかいう風に小説を解釈したいわけではない。私は小説を事実として読んでいるのだから断食芸人は断食芸人だし、バートルビーはバートルビーだ。そして身の回りの「破壊された」人達にも同じようにそれぞれ名前がある。
ミヒャエル・エンデがヨーゼフ・ボイスらと対談した記録を収めた『芸術と政治をめぐる対話』(この書で繰り広げられる二人の食い違いは私にとって大きな問題で、この延長にある問いを一人の作家としては引き受けざるをえないのだが文字数が足りないので今は言及しない)の中で、「私に言わせれば、ほとんどすべての芸術や文学の仕事は、それまで名前を持っていなかった事柄に、名前をつける事なんですよ。名前をつけられれば、人間はその事柄と関係をもてるようになるわけですからね。」と言っている。ちょっと(最近読んでいる)精神分析の話にも通じそうだ。実際隣近所の人に親しく「○○さんや」と日々呼びかけ関係を築いていくことだって、芸術と政治―今ではすっかり別々のもののように語られるようになってしまったこれら―に通じる営為だ。このところ、私たちにはそれぞれ「名前がある」ということが忘れられてきているんじゃないか、生身の人間に対峙することの想像力をもたない人が増えてきたんじゃないか。新しい共同体と強靭な「フィクション」の創造はまだまだ必要だとつくづく思うのである。
 writer:三嶋 佳祐
writer:三嶋 佳祐
1990年生まれ。自己紹介が苦手です。
Twitter:@fuku6fuku6
自己抑制
1ぼくは食べる事も、自分で料理を作る事もとても好きです。去年の五月に実家を出てから、ほぼ毎日自炊しています。日々の生活でほぼ毎日やる事といったら、生理的なものを除くと意外と少ない気がします。
今現在の自分の生活スタイルにおいては、自発的に好きな音楽を聞く事や楽器を弾く事などの、音楽に触れる事、そして先ほども述べた食事を作る事、おそらくだけどこの二つだけ。この二つに関しては、その行動を起こす際に、嫌だな、面倒くさいなと思う事の一切ない、自分の人生にとってもすごく貴重な時間だと思っています。今回は「食」と「音楽」の自分の中での共通点などについて書いていきます。
2.小学生のころ、自分で初めて味噌汁を作りました。豆腐と長ねぎを切って、沸かしたお湯に入れて、何となく火が通った感じになったら、冷蔵庫にあった味噌を入れて、お椀によそいました。何となくそれっぽい味はするのだけど、決して美味しくはなかった。いつも母親が作ってくれるそれとは、正に似て非なるものでした。
今考えると、出汁を一切とっていなかったので、深みとかそういったものが全く無い味だったのだろうなと思います。でも、そういった「美味しくなかった理由」に気付いたのは、初めて作った小学生の頃よりも、すごく後のことでした。それに気付いた時に同時思ったのは、毎日のように食卓に出て来たあの味噌汁は、非常に手間をかけて作られていたという事です。思えば、僕の母親は、必ず粉末だしなどは使用せず、煮干しや鰹節から出汁をとって作っていてくれました。
ぼくが初めて、The Beach Boys のペットサウンズに収録されている「素敵じゃないか」を聞いた時、子供ながらに物凄く感動したのを覚えています。冒頭に出てくるサビのメロディが本当に大好きで、よく歌っていました。しかし後半に出てくる、テンポを下げたコーラスパートが、歌メロに比べるどうにも聞きにくい感じがして、嫌いでした。しかし、ぼくも年を追うごとに色々な音楽を聞くようになり、自分で作曲をしてみたり、曲のアレンジを考えてみたりするようになってから、もう一度歴史的名盤としてペットサウンズを知り、「素敵じゃないか」を聞いてみると、後半のコーラスパートがすごく練られて完成度の高いものに聞こえました。その頃には、あんなに大好きだった冒頭の歌メロパートよりも、断然好きなパートになっていました。ここで、僕は「本当に素晴らしいものは、大衆性と職人的な部分の両方を合わせもっている」という、誰しもが一度は気付くであろう、一つの価値観にたどり着きました。
なぜそこにたどり着いたかと言うと、自分が食事を作ってもらったり、音楽をただただ聞くだけという「受け手」側から、自分でなにかを作って、人に食べてもらったり自分で食べたり、自分で実際に作曲をしたりする、「送り手、作り手」側になったことで、その物事に対してより深く考えるようになったからだろうと思います。自分が生産したり提供したり
する側になることで、初めて、コツや難しさに気付くようになるとうのは、この世のあらゆる芸術や物事においてよくあることです。しかし面白い事に、料理をするようになって僕が一番大切だなと感じたことと、自分で音楽を制作したり、人前でプレイするようになって一番大切だと気付いたことは、同じものでした。それは「自己抑制」です。
自分は、誰かのために料理するとき、人前で音楽を演奏する時、確実に無意識に自分を抑制しています。人間が生活するなかで「自己抑制」は他の行動や生産活動などにおいて、必ず登場するものだと思いますが、料理に関するそれと、音楽に関するそれは、とてもよく似ていると感じています。それは非常に感覚的なものなので、これ以上の説明は僕の能力ではできません。代わりに、音楽と食が、一つの空間の中で見事に同居しているとても好きな音源を紹介します。
3.北京ダック / ハリー細野&TIN PAN ALLEY IN CHINATOWN
曲名はとても有名な中華料理の名前。しかし、曲中でその料理について歌われることはなく、横浜中華街で起きる騒動を喜劇的に描いた、
オリエンタルな一曲。今回選んだものは、1976年5月日に、横浜中華街の同發新館で行なわれたコンサート音源。基本的にラウンジミュージック的な演奏に徹しようとしている感じはするのだが、どこか全体的ドタバタしていて、各楽器のミスタッチも少しある。細野晴臣を初めとしたTIN PAN メンバーや、ベースを弾いている後藤次利は元々ロックやポップスの出身なので、ダンスホールなどで演奏する機会はあったかもしれないが、こういったオシャレなレストランで演奏する箱バンのような経験はあまりなかったのかもしれない。しかしその不完全さや曖昧さがこの「北京ダック」という曲の世界観とマッチしていて、自己抑制的な部分と感情的な部分のせめぎ合いを、すぐそばで感じられるような演奏になっている。とても好きなライブ音源。
「皆さん、どうぞごゆっくり食べていて下さい。音楽はそういうものですから。まだ美味しそうなものが残っているので、食べながら聞いて頂きたいと思います。」細野晴臣がコンサート中のMC で発したこの台詞、意味深で、すこしニヒルで、とても良い。
 writer:加藤寛之
writer:加藤寛之
趣味は楽器を演奏すること。
毎回、一定のテーマで何曲か選曲していこうと思います。
カイロの夜なかの七面鳥
2012年の夏、アラブの春の革命のあとの熱もまだ冷めない頃、アラブの国々の学生と交流する団体に入っていた僕は、エジプトのカイロにいた。滞在中はずっと、アフマドさんという日本の大学に一年間交換留学
に来ていた、少し年上の日本語のとても上手な、そしてとても優しい人にホームステイをさせてもらっていた。初めて訪れる街、カイロは革命後ということもあって、訪れたばかりの自分にも街行く人々に生命力がとにかく漲っているのがわかった。人だけでなくて、街の音̶̶車のクラクションが常に鳴り、人々の笑い声、話し声、礼拝のためのアザーンというお祈りがずっと̶̶̶街に響き、そして街を行き交う動くものたち、車の往来、少しの隙間さえあればすり抜けていくバイク、チャリ、さらには馬車、ロバ車?犬や猫、鳥、、、̶̶̶とにかく何だか1秒間に起こる出来事が日本の3倍は多いような気がする情報量なのだ。
そんな街で、僕が泊めてもらうことになっていたアフマドさんの家(お兄さんがかつて住んでたアパート)はカイロから電車で40分くらいのかなりのダウンタウンで、駅に着いた後、10分くらい二輪のタクシーを拾い、乗せてもらって家に向かった。ドアがないから座っている横で、風を切って街の景色が流れていく。人々が水タバコを吸いながらコーヒーを飲み、トランプなのか、カード遊びをしてる次にはカゴの中に鳥がいて、主婦のような人に選ばれているとその鳥が肉屋の店長によって鳥肉になっている光景にビビった後、子供たちがサッカーや走りまわって遊んで、普通に笑ってることに和んだりして、そうした時間が続き、アフマドさんのアパートに着く。
部屋のある7階まで階段で登って、ドアの前に着くとアフマドさんが何やらかなり焦っている。部屋の鍵を忘れたらしく、すぐ戻るからーと言って走って実家に鍵を取りに戻ってくれた。その間ポツンとアパートの屋上に上がり、ぼんやりと上からカイロの街を眺めていた。8月、日中は日差しが強く本当に暑いのに、夕暮れになると乾いた涼しい風が吹き、とても心地よかった。日が暮れて薄い月が見えた。そうやってなんとか黄昏つつも若干不安になり始めると多分アフマドさんの隣人おばさんが来て、冷たいレモンの飲み物をくれた。アフマドさんがドアの前でガチャガチャしている時に何か異変あると思ったのだろう、その後に日本から来ている学生に何かしてあげようと思ったのか、心遣いが嬉しかった。
3日ほど経って、ちょっとずつ街にも慣れてきた頃、カイロからアレクサンドリア図書館で有名なアレクサンドリアに電車で行って帰ってきた。その夜はアフマドさんはあいにく仕事で忙しく、駅から迷路のようになっている家まで、アフマドさんの導きなしに帰った。
そのアフマドさんのそのフッドでは日本人はあんまり見慣れないらしく、子供たちがジャキー・チェン!とか言ってくるのをうまく逃げ切り、家に着く。疲れたし今日は寝ようかという時に人が帰ってくる音がして、アフマドさんも仕事が早く終わったのかと思っていると全然知らない人が入って来た。さらにその全然知らない人もこっちを見て全然知らない人がいると思ってるようで、お互いが驚いていた。どうやら滅多に帰ってこないお兄さんが帰ってきたらしい。怪しまれないようにたどたどしい英語でコミュニケーションを試みるが全然通じない、英語力の問題かと思ったけれど英語自体が通じないようだった。そして困ったことに僕はアラビア語が話せなかった。(ちなみにエジプトは若い人は英語がかなり上手かった。フランス語も話せる人が多いのにも驚いた)仕方がないので身振り手振りでシンプル英単語、知ってるアラビア語を駆使してなんとかコミュニケーションする。自分を指差して「アフマドズフレンド!」ということを全力で連呼するとなんとかわかってくれた(ような気がした)。「弟は日本語の勉強をしているし、日本の友達が来てるんだな」ということが了解され、そこからはイエス、ノー、サンキュー、オーケー、グッド、シュクラン!(ありがとうございます)と言った語を駆使。
そんなどきどきする攻防の後、ちょっとお互いが面白くなってきて、打ち解けてきた。満足し、「本当に泊めて頂きありがとうございます、今日は遅いのでそろそろ寝ますね。また明日に話しましょう」ということを伝えようとするとお兄さんもなんかすごいアラビア語で話しかけてくれて、イェー、とか相槌を打つと、部屋を出ていってしまった。グッドナイト的なこと伝えようとしたけれども出来ずに部屋で待っているとクリスマスの七面鳥のような皿いっぱいの鳥の丸焼きを持って現れた。それを僕の前に差し出し、「さっき言ってたやつ」みたいなことを言ってその目はお熱いうちに食べなさいと言っているのだった。
正直お腹も全然減っていなく、全然食べれる気がしなかったが、断るのも悪いし、初めて会ったほぼ見ず知らずの僕に心からの善意からしてくれたことを断りたくなかった。半ば無理して食べることになったけれど、お互い言葉が通じない人間同士でその鳥を囲んで一緒に食べた鳥の丸焼きは本当に美味しかった。
5年後の今、まだ自分はアラブの人々とどうにかして関わっていたいと思っているのは、きっとああいう夜があの後、幾度もあったからだ。そしてあの時、季節外れの七面鳥に贈り物をもらった気がして、まだ恩返しの仕方を考えている。
 神宮司 博基
神宮司 博基
音楽が好きな青年、大学院生。