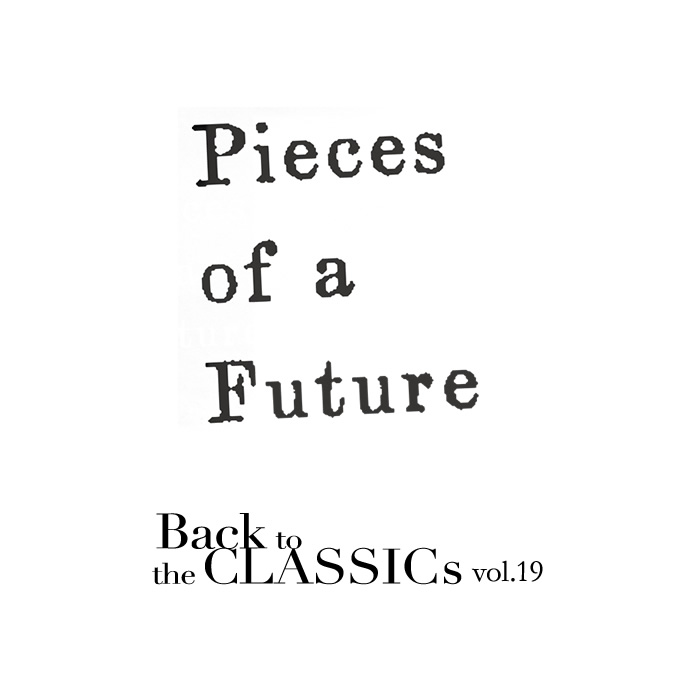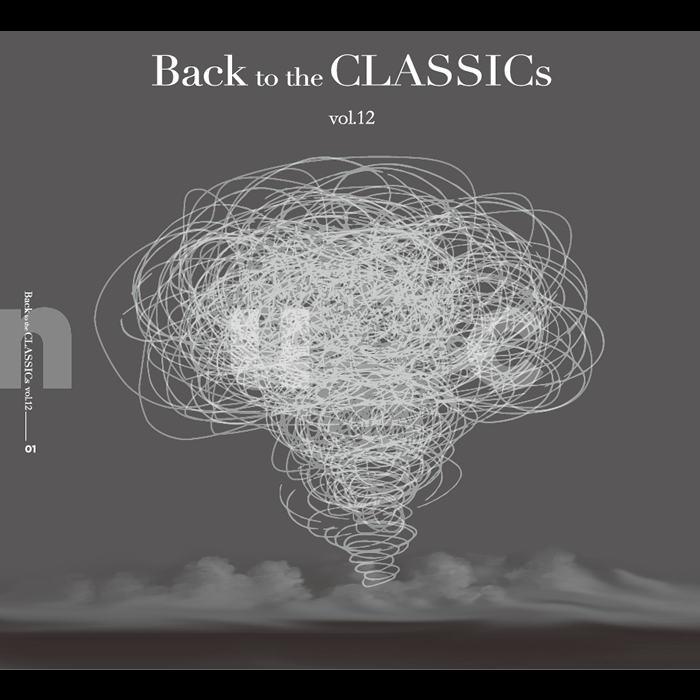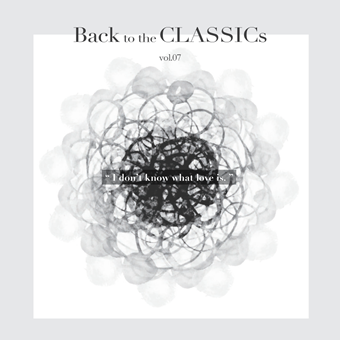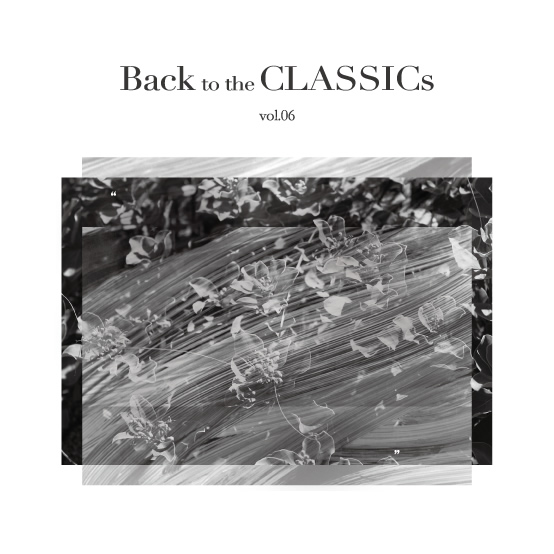
Back to the CLASSICs vol.06
“こうして小町娘のレメディオスは、十字架を背に追うこともない孤独の砂漠をさまよい、穏やかな睡眠と、きりのない沐浴と、時間のでたらめな食事と、思い出を知らない長くて深い沈黙のなかで、一人前の女に育っていった。
やがて迎えた三月のある日の午後、紐に吊るしたシーツを庭先でたたむために、フェルナンダは屋敷の女たちに手助けを頼んだ。仕事にかかるかかからないかにアマランタが、小町娘のレメディオスの顔が透き通って見えるほど異様に青白いことに気づいて、「どこか具合でも悪いの?」と尋ねた。
すると、シーツの向こうはじを持った小町娘のレメディオスは、相手を哀れむような微笑を浮かべて答えた。
「いいえ、その反対よ。こんなに気分がいいのは初めて」
彼女がそう言った途端に、フェルナンダは、光をはらんだ弱々しい風がその手からシーツを奪って、いっぱいに広げるのを見た。
自分のペチコートのレース飾りが怪しく震えるのを感じたアマランタが、よろけまいとして懸命にシーツにしがみついた瞬間である。小町娘のレメディオスの体がふわりと宙に浮いた。
ほとんど視力を失っていたが、ウルスラひとりが落ち着いていて、この防ぎようのない風の本性を見極め、シーツを光の手にゆだねた。めまぐるしく羽ばたくシーツに包まれながら、別れの手を振っている小町娘のレメディオスの姿が見えた。
彼女はシーツに抱かれて舞いあがり、黄金中やダリヤの花の漂う風を見捨て、午後の四時も終わろうとする風の中を抜けて、最も高く飛ぶことのできる記憶の鳥でさえ追っていけない遥かな高みへ、永遠に姿を消した。”
Gabriel García Márquez-Cem Anos Solidão
音楽、夜から朝を迎えるために。
何も出来なくなって、眠る以外には何もしたくなくなる時がきっと誰にでもある。僕にはある。そんな時でさえも、ある種の音楽だけは不思議と聞くことが出来る。そのことを救いと言っていいのかはわからない。しかしそういう時音楽だけは、確かにこの世界には美しい物事が存在していることを教えてくれて、光に似た何かをもたらしてくれる様な気がするのだ。
そうした音楽にはある日出会う。それまで全く知りもしなかった人が作った未知の音楽が、ある時から特別な存在になって救いをもたらしてくれる。そのようにして、Oren Ambarchiという、もしかしたらほとんどの人が知らないかもしれない音楽家が作った音楽に、僕は救われてきた。
始まりはこうだ。ジョン・フルシアンテというレッドホットチリペッパーズの元メンバーの音楽が大好きだった僕は、彼を特集した本を手に入れて熟読してた。そこにはインタビューなどと共に、彼の音楽を深く知るためのディスクガイドというものがあって、彼が影響を受けたというジミヘンやザッパ、Aphex などのよく見知った名前が並べられていたのだけれど、同時に全く聞いたこともなかった人たちも並んでいた。Rafael ToralやRosy Parlane,Oren Ambarchiなど、いわゆる音響派と呼ばれるような実験的な音楽を作る人々だ。
僕は、ジョン・フルシアンテについては何でも知りたいつもりだったのでそうした名前を全然知らなかったことにショックを受けつつ、それらのCDを探しに行って、何とか手に入れて聞いた。
でも、最初は聞いても正直あんまりよくわからなかった。音波というか、何だか分からない音がずっと続いて、ふと終わる。「これは音楽なのか。笑」 そんな感じだったけど、ジョンが好きな音楽が分からないことが悔しくて、しばらくずっとこうした音楽を聞いていた。———キャプテン・ビーフハートの時もそうだった。最初は完全に狂人がめちゃくちゃにやってるようにしか聞こえなかったけど、ジョンはこれを一日16時間聞いていたと知って、我慢して毎日5時間くらい聞いていたら、ある時ふと二本のギターの音が違う旋律を奏でて、それが複雑に絡んで音楽を作っていることに気がついた。その瞬間から全然違う風景が見えて来て、理解できた気がした。その後にはなぜかバッハを聞いてもわかるようになった。複数の異なる旋律が絡み合う音の美しさに気づいたのはあの時からだ。
それと同じように、新しい発見があるだろうと思って聞いていたら、徐々にその音楽は音で彫刻を作っているような、インスタレーションのようにある美的な空間を生み出しているような気がしてきた。そうやってまた耳を澄ませると、自分がいる場所と全然違う場所に連れられる気がした。
その中でも、ある曲に強く惹きつけられた。Oren Ambarchiの“Remedios the Beauty”という曲だ。本当に謎めいた魅力があって、とても印象的な美しいメロディで始まるのだけれど、それが、何を使って生み出されたのか全く見当がつかない。普通の楽器やシンセサイザーとは明らかに違う不思議な質感で、深い森のような、それとも心臓の鼓動の音のような、でも優しい音楽だった。
その題名も何を意味しているのか、すごく謎だった。美しいレメディオス?レメディオスは人の名前だろうかと、想像しながら聞くと、そのレメディオスがまだ朝ではない夜の終わり、新しくてまだ弱い光の中、森を通り抜けていくような情景が思い浮かんできた。なんのことはなく、きっと自分がそんな時間によく聞いていたからかもしれない。それでも聞けば、どれほど不安な、やるせないような気持ちの時にも、不思議と穏やかな気持ちになれた。
それからはレメディオスが一体何なのかずっと気になっていたのだけれど、最初は調べてすぐに出てきた「レメディオス・バロ」というスペインの女性の画家のことかと思っていた。しかし彼女の絵を見てもなんとなくイメージと違っていて、ずっともやもやしていた。
それが最近、わかったのだ。外国語を少しは読めるようになってから、ふと思い立ちもう一度調べてみると、touchというOren AmbarchiのCDを出しているレーベル(本当に美しいレーベルで、ため息が出るほど素晴らしい音楽に溢れている)のページに、このアルバムに寄せられた英語のレビューがたくさん載っていた。それを読むと、何やら、Remedios the beautyはガルシア・マルケスの小説、『百年の孤独』の登場人物のレメディオスから来ていると書いてあって、とても驚いたのだった。
なぜ気づかなかったのだろう?あの『百年の孤独』のレメディオスだったのか!ブエンディア大佐の幼いまま亡くなった妻、レメディオスの胸が切なくなるようなエピソードを強く覚えていた。そして同じ名前を持って生まれた、天衣無縫の美しすぎて、本当に天に昇ってしまった小町娘のレメディオスのことを。この「小町娘のレメディオス」が、英訳ではRemedios the Beautyというらしく、それを知ってなぜだかとても嬉しかった、繋がった気がしたのだ。自分が夜夜中、朝になる前のあの時間に聞いて心を慰められていた音楽と、世界で最も偉大な小説の一つで、自分の家の本棚にもあった物語が。そしてそれに気付かれるのを、待ってくれていた気がした。
自分が好きな曲は、光をはらんだ弱々しい風がその手からシーツを奪って、いっぱいに広がるような、そうした風と一緒に宙に浮いてどこまでも高く登っていってしまうような、そんな名を持つ音楽だったのだ。
それを知ったところで、どうしたということもないのだけれど、僕はこれからも夜になるとこの音楽を聞くだろうと思う。そうしてこの世界には確かにまだ美しいものがあることを確認すれば、小町娘のレメディオスも光をはらんだ風で空に見えなくなって、いつしか朝を迎えている。
神宮司博基
1989年、東京生まれ。
音楽好きな青年。大学院生。Fethi Benslamaの研究。

待ち合わせの約束
ヴラジミール むだな議論で時間を費やすべきじゃない。( 間。激烈に ) なんとかすべきだ。機会を逃さず ! 誰かがわたしたちを必要とするのは毎日ってわけじゃないんだ。実のところ、今だって、正確にいえば、わたしたちが必要なんじゃない。ほかの人間だって、この仕事はやってのけるに違いない。わたしたちよりうまいかどうか、そりゃ別としてもだ。 われわれの聞いた呼び声は、むしろ、人類全体に向けられているわけだ。 ただ、今日ただいま、この場では、人類はすなわちわれわれ 二人だ、 これは、われわれが好むと好まざるとにかかわらない。この立場は、手おくれにならないうちに利用すべきだ。運悪く人類に生まれついたから には、せめて一度くらいはりっぱにこの生物を代表すべきだ。どうだね ?
エストラゴン 聞いてなかった。
ヴラジミール 確かに、事の賛否を、両腕をこまぬいてゆっくり考える ことも、同じく人間の条件を尊ぶことではある。これが虎かなんかなら、少しの反省もなく仲間の救援に駆けつけるだろう。でなければ、ただち に草むらの奥に逃げ込む。だが、問題はそこにはない。われわれが現在ここで何をなすべきか、考えねばならないのは、それだ。だが、さいわ いなことに、われわれはそれを知っている。そうだ、この広大なる混沌 の中で明らかなことはただ一つ、すなわち、われわれはゴドーの来るのを待っているということだ。
エストラゴン そりゃそうだ。
ヴラジミール でなければ、夜になるのを。( 間 ) われわれは待ち合わせをしている。それだけだ。われわれは別に聖人でもなんでもない、しかし、待 ち合わせの約束は守っているんだ。いったい、そう言いきれる人がどれくらいいるだろうか ?
エストラゴン 数かぎりないね。
ヴラジミール そうかな ?
エストラゴン よくはわからないけどな。
ヴラジミール そうかもしれない。
ポッツオ 助けてくれ !
いまでも思うのは、ISISに殺害された後藤さんと湯川さんのことだ。彼らはあそこにいて、人類全体に眼差しを向けていた。僕はここにいて、テレビ越しにゴドーを見たのかもしれない。待ち合わせの約束をしていたのかもしれない。「待ち合わせの約束は守っているんだ。いったい、そう言いきれる人がどれくらいいるだろうか?」
(参考)サミュエル・ベケット『ゴドーを待ちながら』
(安堂信也・高橋康也訳)、白水社、2013 年。
牛田悦正
Rapper(Tha Bullshit) / Writer

文学の楽しみ
時代の危機に抗してか、巷には「反知性主義にならないために」であるとか、 はたまた時流に乗り、コミュニケーションを円滑にするための「教養」であるとか、とかくそういった本が目につくことが多い。 かくいう自分も、そういった例に漏れず「知性的」であろうと志向しているし、 「教養」があるならそれに越したことはないと思う。
そういったときに、人は必ず本に向かう。哲学、思想、宗教、自然科学、歴史、文化、政治経済……。しかし、その中で、そうした目的のために向かおうとすれば失敗することが目に見えているものがある。それは文学であり、なぜなら、それがある楽しみを必要とするからである。 小説でも詩でもいいのだが、常からそれらに親しんでいる人からすればもって当たり前のことが、「鹿爪らしく」考える人にとってはそうでないことがある。 つまり、言葉が生きているのを認めることができるかどうかということだ。
手元にある本をざっと眺めてみればいい。アンダソンの描くある街の様子を、 チェーホフの描く子どもたちを、あるいはカフカ。測量士Kの現実を。一人の読者として、こうしたものを目の前にしたとき私たちがするべきことは、書かれていたことを抽象し、他のものへと還元する作業ではない(するとたちまち 生きた言葉は「ただの活字」へと変わる)。そうではなく、その言葉の肌理を、 言葉によって立ち現れた現実を味わい尽くすことなのだ。文学という「言葉を極限まで生かす」方法に接したとき、私たちは勉強になったとか情報を得たとかいう前に「先ず精神が鳴り響くのを感じ」る。文学を駆動するのはこの喜びこそである。
情報か、知識か、あるいはコミュニケーションか、現在ますます私たちは言葉とともにある。しかしたとえば、それが生きて躍動しているとしか考えられないような言葉があるということを今でも人は忘れずにいるだろうか。それならば、人はこの楽しみを知らなければならない。
吉田健一『文学の楽しみ』
講談社文芸文庫(2010年)
小林 卓哉
1992年生まれ。大学在学中、保坂和志とロラン・バルトに感銘を受け文学に強い興味を抱く。現在都内で販売員をする傍ら執筆中。

配達不能郵便、または書物
私は書物を愛している。その頁、そして、その余白に書かれていることを愛している。あの小説に登場する、または決して登場しなかった、彼らや彼女たちのことも愛してやまない。
幾人かの彼らや彼女たちの名前は知っている。例えばジーモン・タンナー、ウェイクフィールド、ブヴァールとペキュシェ、エミリー・L、テスト氏…。それでもやはり、名前を知らない人達の方が圧倒的に多いけれど。カフカの断食芸人の名すら知らなければ、フェルナンド・ペソアの異名だって全ては知らないのだから。
そんな私の文学的星座の中の一番星の一つとでも言うのだろうか、いや、一番星が複数あっては困るから、オリオン座で言えばベテルギウスかリゲルのような存在、と言えば伝わるだろうか、それがバートルビーだ。
1853 年に発表された『バートルビー』は、アメリカの作家ハーマン・メルヴィル(1819-1891) による、とある法律事務所に代書人として雇われた青年バートルビーを巡る小説である。語り手はこの法律事務所を営む年配の男だ。
バートルビーは筆耕以外の振られた仕事を全て「せずにすめばありがたいのですが(I would prefer not to)」という、柔らかい否定の言葉で退ける。彼はやがてその筆耕の仕事さえも拒むようになり、クビを言い渡されても事務所から出ていこうともしない。一向に動 かない彼を置いて事務所を移すも、前の建物の持ち主から語り手のもとに、彼が建物から離れようとしないと苦情がくる。あらゆる申し出を断り続けたバートルビーは遂に警察に連れられてしまうが、食事をも拒み、刑務所で息絶えてしまう。その後語り手はバートルビーがそもそもは郵便局の配達不能郵便を扱う部署で働いていたことを知る。
あらすじで言えばそんなところだが、小説は「あらすじ」や「ストーリー」を追うものではないのだから、是非『バートルビー』のテクストの中で彼と出会ってほしい。
彼に魅了された多くの人が、彼を巡るテクストを書いた。(また、書かなかった。)ブランショ、アガンベン、ドゥルーズ、デリダ、ジジェクら哲学者たちのバートルビー論も刺激的だが、私のお気に入りはスペインの作家エンリーケ・ビラ=マタスが 2000 年に発表した小説『バートルビーと仲間たち』だ。小説の語り手(彼自身もそうなのだが)が様々な事情から「書けなくなってしまった」数多の作家たちを取り上げ、種々雑多なエピソードと合わせて書き溜めたメモという体裁の小説である。「書けなくなった作家たち」は作中で「バートルビー症候群」と呼ばれる。
私は 25 にもなってプラプラしているので、人から「一体何になりたいの?」などとよく訊かれる。半分ふざけて「特になりたいものはありません」とか答えるのだけれど、そういう質問を受ける時、バートルビーのことを思い出す。
勿論その質問が「どういう職に就きたいのか?」とか「何を生業にしていくのか?」ということを訊いているのはわかっていて、その上で「その手の質問があまり好きではありません」の意志表示を兼ねたつもりでお茶を濁すのだが、そういう時、バートルビーならなんと言うだろう、とふと思う。「(何かに)ならずにすめばありがたいのですが」、「(何かに)ならないほうがいいのですが」だろうか、なんて。
当たり前のように「自分は何者かである、何者かであらねばならない」というアイデンテ ィティへの信仰が犇く世間で、ふと「何者でもない」ということを思い出す時。それは虚しいことのようにきこえるかもしれないけれど、私にはこれ以上ない救いのように思える。「自分が何者かわからない」ことよりも、「何者かである」という状態の方がよっぽど健忘なのだから。
現代社会が称揚してきた「役に立つ」とか「経済的である」とか「理にかなっている」といった価値では決して計れないものを肯定する場所が小説も含む諸芸術にある。そしてそれはなんだか特権めいた響きで持て囃される「ブンガク」や「アート」などではなく、誰もが持っている、私たちの生活の中に遍在しているそれらのことだ。即ち「ただ生きる」という野性から生まれくるもの。私たちが大人になる前の未分化な感情を保持していられる場所。
あらゆる権威の放棄など、不可能な夢かもしれない。それでも私は彼に救われ、彼のように地に足を付けたまま飛翔するような在り方というものを、だらだらと過ごしてなんにも出来なかった一日の内に想ったりする。
時々『バートルビー』を開いて、その頁の余白をしばらく眺めてみたくなる。
書かれなかった言葉を乗せた白い一隻の破船が、波に乗って溶けてゆくのを幻視する最中、その無口な板きれがまだ根を伸ばし生きていた頃の姿を想った。これが恢復でなくて、なんであろう。
配達不能郵便は、確かに届けられたのかもしれない。
引用はハーマン・メルヴィル 『代書人バートルビー バベルの図書館 9』 ホルヘ・ルイス・ボルヘス編、酒本雅之訳、 国書刊行会、1988年より。
三嶋 佳祐
1990年山口県生まれ。作家(志望)。ゆだち というバンドで作詞作曲等。趣味は家にいることと散歩。自己紹介が苦手。
Twitter:@fuku6fuku6