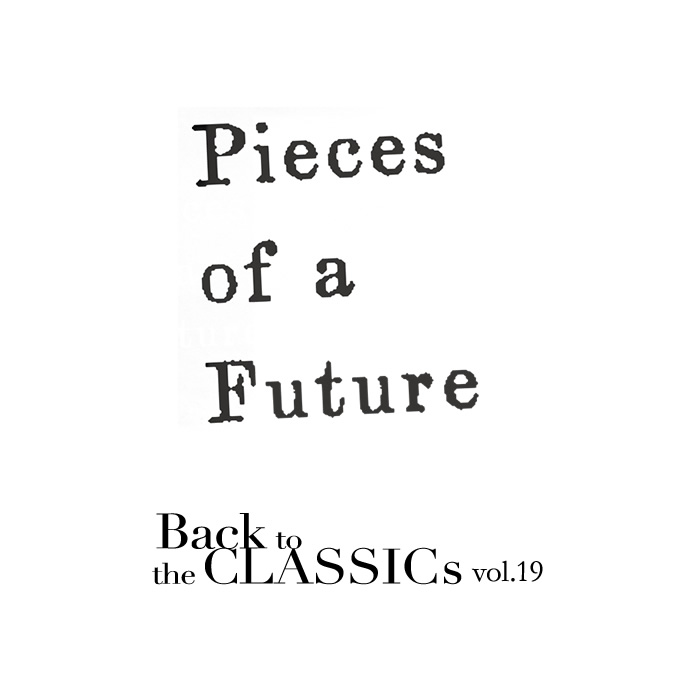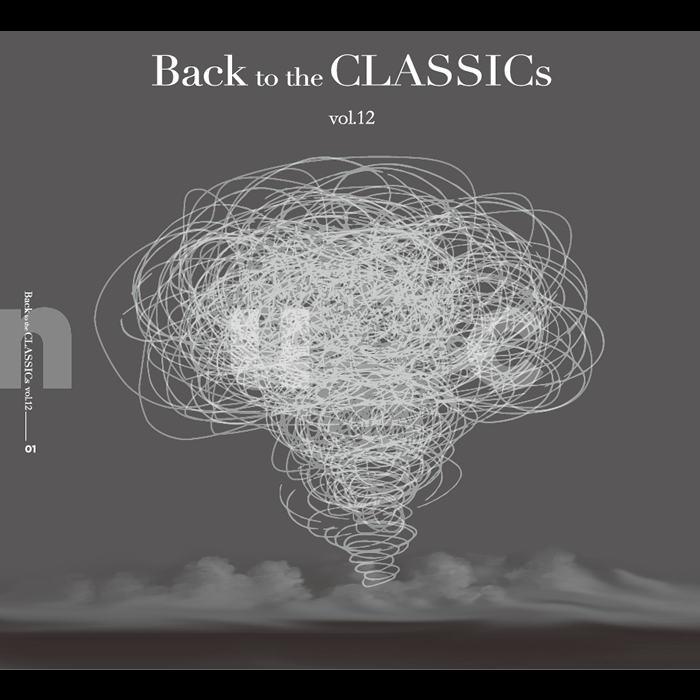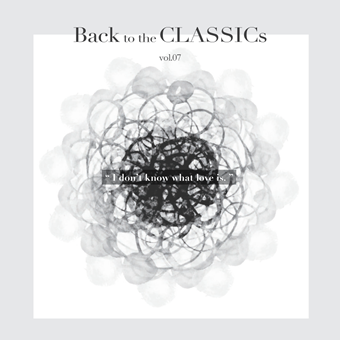Back to the CLASSICs vol.09
そして、今回からBack to the CLASSICs は、代官山ティーンズ・クリエイティブと連携してCLASSICs S ession for U25 というイベントを開催します。毎回、連載に関連したゲストを呼んで、お話を聞きながら来場者をいまだ見知らぬ世界に繋ぐ場にしたいと思っています。初回のゲストは、探検家、人類学者である関野吉晴さんに決まりました。イベントコンセプト、および詳細は後半のイベントページをチェックしてもらいたいです。
今日、私がりんごの木を植えること -生きのびるための“ Do It Yourself ”
もし明日、世界が破滅するとしても、今日私は、私自身のりんごの木を植えるだろう」というマルティン・ルターが言ったとされる言葉がある。そのルターとキング牧師が同じ名前だったということを知ったとき、不思議に印象深い思いがした。Martin Luther とMartinLuther King,Jr. この繋がりに何だか理由もなく、世代を越えて植えられたりんごの木は渡されるんだと思えたのだ。自分でりんごの木を植えること。明日が来ても、来なくても。毎日いかんともしがたいことばっかりあるように思えるとき、ふとこの言葉を思い出す。
* * *
石山修武さんという建築家の人が書いた『生きのびるための建築』という相当面白い本がある。20歳少しの頃、自分はどうやら全然、生き延びられなそうと思ってたとき、本屋で手にとって、そこで語られる自分が全く知らなかった希望の持てる話の数々に、もしかすると探そうとしさえすれば、違う道や可能性というものは見つかるんじゃないかという気持ちになれたことがあった。
この本には、建築を中心として「生きのびるための」道を考えるために今必要な考えを教えてくれる人たちの話が詰まっている。バックミンスター・フラー、ル・コルビュジェといったビックネームと共に、未だ多くの人々には知られていない隠された可能性を示す天才たちの話が特に面白かった。
ロサンゼルスのスラム街ワッツで33年かけて見よう見まねでガウディのサクラダ・ファミリアを真似して作っちゃったイタリア系移民のおじさんサイモン・ロディア。海に漂流して打ち上げられた材料だけで家を建てた無名の漁師・伴野一六。独学で世界的なエネルギーの知識を得てノアの方舟のような家を建てた本物の天才、川合健二といった話の数々。
そんななか、強く惹きつけられたのがバックミンスター・フラーの話だった。彼は発明家、デザイナー、建築家といった多岐にわたって重要な仕事をして来た人で、『宇宙船地球号操縦マニュアル』という本にあるように、この地球がひとつのかけがえのない星であり、有限な資源を持って飛行する宇宙船であるのだから、そのなかで共に生きるためにはどうしたらいいかを考えた人だった。そして何より、この地球を守るためには企業とか、誰か他人に任せるんじゃなくて“Do it yourself”̶̶自分でやってみようという考えを生んだ人だった。
そんなフラーの思想を基にして、1960 年代後半、アメリカのヒッピーたちはある雑誌を作った。1968 年、“Whole E arth Catalog”という「全地球カタログ」と名付けられた雑誌だ。たった4ドルの、はぐれものたちが作った雑誌は当時聖書よりも売れて、アメリカの文化にD.I.Y. という思想を根付かせる大きな影響を与えた。そうして「企業や、教師や、誰かに与えられたものじゃなくて、自分でやってみよう、君が作ってしまえよ」という考えを世界に広めることになった。
第一号の表紙には、青い地球の写真が写っている。驚くことに、このとき表紙に丸い地球の写真が飾られるまで、地球の全景は軍事的な機密としてほとんどの人は見たことがなかったらしい。それをヒッピー編集者スチュアート・ブランドがNASA に「写真出せ!」と言って地球をみんなに見せることが実現した。「宇宙船地球号」という思想に影響を受けたこの雑誌にあっては、自分たちが乗り込んでいる宇宙船が確かにひとつで、青く美しいかけがえのないものだというイメージは不可欠だったのだ。
「この本は僕たちを『消費』に向かって駆り立てるためのものではなく、僕らが地球という惑星の上でヒトとして自立して生きるための手がかりを提供しようとしている」、そういう志から生み出されたこの雑誌は“Access to tools”(道具へのアクセス)というコンセプトで様々な道具を紹介している。ページをめくれば、自然のなかで生きるために必要な道具、その使い方、そして役に立つ考えを記した本などの情報が満載で、そこに載っていた物は実際に通信販売で買えた。
「道具はここにある、それを使って物を生み出すのは君だ」そんなメッセージを持ったこの雑誌を手にとった若者の一人に、大学を中退したシリア系移民の息子、スティーブ・ジョブズがいた。彼はこの雑誌に影響を受けて、自分自身で物を作り出す勇気を得たことを有名なスピーチで言っている。“Stay Foolish, Stay Hungry”̶̶そして彼が作ったりんごの印がついた機械で今、わたしは文章を書いている。
* * *
流れていく毎日のなかでふと思い出す、木を植えること。自分にはもう無理だと思えるとき、それでも種は手にあることに気づく。本に、音楽に、絵や、映画に心を動かされてしまっている自分がいるとき、今日まで生きのびている自分に気づくとき。今はまだないように見える果実のために種を植えて、木を育てようと決めるなら、時を越えて違う景色が生まれる希望は消えない。
 神宮司 博基
神宮司 博基
1989年東京生まれ、音楽の好きな青年。大学院生。 Fethi Benslama、フランスのムスリム系移民の研究。本を読み、良い音楽を掘り進め探す毎日。
恢復するブリコラージュ
つまりは以前コミュニケーションの問題で申しましたが、情報化というものは他者性を去勢するものですから、この「情報化された他者」には実は既に「他者性」はないのです。(中略)この「他者性」の感覚欠如によって私たちはローカル(特殊)なものであります西欧的歴史を何ら断絶感も違和感もないままに連続化させ引き継いでいるという観念的な「錯覚」に陥りやすいということなのです。
‐中島 智『文化のなかの野性』より
「情報化」とここで言われていることは、他者を一義的な枠組の中に押し込めること、自分が既に知っている言葉で説明できると思うことだと言い換えられるだろう。「他者性」とは、わからなさ、である。他者を既に知っている言葉で説明できると思うことは他者性を去勢する、全くその通りで、他者とは本来的に距離があるものだから他者なのである。
では、他者を少ない枠組に閉じ込めない思考の在り方とはどういうものだろうか。例えばレヴィ=ストロースが『野生の思考』の中で「ブリコラージュ」と呼んだ知の在り方がある。ブリコラージュとは人間が何かを作る時の根源的な思考の在り方で、ありあわせのモノ(道具や素材)を流用して作ることを言い、あらかじめの計画に即した材料を調達してから作る「エンジニアリング」の在り方とは対置される。
例えば私は幼い頃、祖父母の家の朝刊に挟まれていたチラシを捨てられてしまう前に回収してその裏に絵を描いたり、空になった蜜柑のダンボール箱を切り出してなんだかよくわからないものを作ったりしていた(具体的に何かを作ろう、というよりは、切ったり組み合わせたりする過程に夢中だった)。藪の中に秘密基地を作る時は、捨てられているボロ傘やビニールシートを雨よけに木の枝にかけたり、木の実や花のついた枝で飾り立てたりした。まさに全てブリコラージュであり、似たような経験は誰しも覚えがあるだろう。
このように、ありあわせのモノを流用するということは、モノに多義性や多面性を見出すことだ。もっとくだいて言えば「他の使い道もあるなあ」とか「まだ他のことに使えるなあ」と考えることだ。これは本来的にはわからないものであるはずの他者を既にある枠組に押し込める考え方とは反する。
当たり前だが例えば鉛筆を生まれて初めて見た人にその一般的な文字や絵を書くという使い方がわかるとは限らない。その時、鉛筆はその人にとっては未知なる他者だ。鉛筆を初めて触る人のようにして触る、目の前のモノの「他者性」をそのままに思考することこそ多なる可能性をひらくことであり、狭い意味でのものづくりや芸術に限らず肝要な態度ではないだろうか。私たちは何度も「知らない」ということ、他者には他なる文脈があるということを思い出す必要がある。誤解を生む言い方かもしれないがこれは、何も知らないことこそ自由で、理解なんてできなくて当然だ、と、そこで考えることをやめていいということではない。寧ろこうしたブリコラージュ的思考は相手がモノにしても人にしても、しぶとく、長い付き合いのなかで様々な可能性を見出していくということで、いつもいつも完全にゼロから考えるということではないし、そんなことができるとも思わない。
ブリコラージュは時にD.I.Y. という言葉と同義でつかわれるけれど、そっちの方は「self= 自分で」やるという意味合いがはっきり出ている。だが、芸術家は寧ろ「自分自身」ではないものの声を聴く、或いは自分自身の中にも住まう他者と共に歩みを進める。慣習的で情報化された思い込みの外に出ていくということだ。いつも、何故だかわからない、を生きている。新たな、というより、違う生、他の可能性を芸術は恢復する。その営為を愛と呼ぶのは短絡であろうか。まあ、短絡でもつまらない議論であっても、私は私がそう呼ぼうと思うのだからそれでいい。私にとっては言葉さえもブリコラージュの道具だし、意味に厳密に語ろうとも思わない。
もちろん芸術家やその研究者、批評家などの中にも「西欧的歴史」やアート業界の価値観に従順に並走する人たちはいるけれど、芸術はそうした既製の歴史観や価値観、業界の約束事や、世の真理とやらとは「他の」可能性を常に生み出し続ける。どうしようもなく。「私たちが芸術をもっているのは、私たちが真理で台無しにならないためである」と言ったのはニーチェだったが、「ためである」と目的論的に言い切ることはできないまでも、「真理と呼ばれるものから逃げることを可能にする」とは言えるかもしれない。芸術によって生み出されるものは一見、外から眺めればわからないものに見えるかもしれないが、常になにものかでは在り続ける。少なくともそれを一つの場所に止め置くことはできないのだ。誰によっても。
 writer:三嶋 佳祐
writer:三嶋 佳祐
ゆだちというバンドで音楽活動、アルバム『夜の舟は白く折りたたまれて』を全国リリース。音楽、小説、美術など様々な制作活動で試行錯誤。書物、蒐集、散歩、アナログゲーム、野球を好む。広島カープのファン。
藝術の種を育てること、生きるための風景について -ドキュメンタリー映画『息の跡』評
誰にも求められていないのに、勝手に自分でなにかをはじめてしまうこと。『息の跡』というドキュメンタリー映画の中に出てくる佐藤貞一さんは、陸前高田で種屋を営みながら、3・11 の体験を英語や中国語、スペイン語で書き、自分で本にまとめ自費出版してしまう。震災の記録を残そうという人はたくさんいる。でも、そうした試みは、東京をはじめとして、よそから来た人に求められるものであったりする。佐藤さんの試みがそれと少し違うのは、誰に言われたわけでもなく、いわば勝手にはじめてしまったことにある。震災後に突然勉強をはじめた佐藤さんの英語は特別上手いわけでもなく、英語で書くからといって日本の悲劇を世界中に語り伝えようという意識が高いわけでもない。「聞いてくれよ」。「分かるか、分からないだろうな」。そうやって、カメラをまわしている小森はるか監督に話しかける佐藤さんは、自分の体験が誰かと共有出来るものでないことを知っている。それでも佐藤さんの言葉は、宛先のないままどこかに向かって書き続けられる。
「すべて消失した。たくさんの人がこの世界に悔いを残し別の世界に行ってしまった。写真は津波のあとの店の周辺」。佐藤さんは、自分で書いた文章を毎朝、大きな声で朗読し、最後に手を合わせて祈る。映画の冒頭におさめられたこの朗読シーンは、まるで民話のような語りでもあるが、朗々と英語で発せられた声がまるでハリウッド映画のはじまりをも思わせる。しかし、この映画には流された街や、海、といった震災の被害を伝えるスペクタクルな映像はあまりない。その代わりに、種屋さんという小さな小屋から見た、佐藤さんの生活の風景だけが映されていく。それは、東京から見た陸前高田の風景ではなく、そこに住む人から見た生きるための風景であろう。監督の小森はるかもまた、そうした風景を陸前高田に住むことによって発見したという。たとえば「あそこの家はまだいいよ、柱が一本残ってたんだから」という佐藤さんの言葉。機能としての家があるかないか、といったことの間にある住むこと、生きることのリアリティがそこにある。佐藤さんの生活には、さまざまな手作りの「モノ」が溢れている。変な棒の先っちょに括りつけられたへのへのもへじ、チョコレートの空き箱でつくった苗の入れ物、給水器に書き込まれた顔。そこにアニミズム的な神が宿っているわけでもないが、ひとつひとつの「モノ」がとても大切に使われて、他に変えようのない生活空間が形作られていることがわかる。わたしたちの生活空間には、毎日おなじ時間を過ごし、ともに生きる「モノ」たちが満ちている。それを失うことは、全く違った生を生きなければいけないということだ。それは自分と言えるのだろうか。この意味で「モノ」たちはわたしたちの一部である。風景とは、わたしたちが生活し生きるための「モノ」たちに満ちた世界であり、わたしがわたしであるためのふるさとでもあるのではないか。
だから、この映画を他の記録映画と同じようにして、声高に「震災から6 年経った今こそ見るべき映画だ」なんて宣伝することなんて僕には出来ない。それは、佐藤さんや小森さんがその土地に住んでいるからこそ見えてくる、生きるための風景を歪めてしまうように思えるからだ。むしろ、この映画は大切な人にそっと手渡したくなる手紙のようなものである。佐藤さんがなぜ英語で書かなければいけなかったのか、そこに明確な理由はない。同じようにして、震災への特別な関心があるわけでもない小森監督がそうした語りを拾いに行くことに明確な理由があるわけでもない。しかし、それは震災がなければ生まれなかったものでもある。明確に因果関係を結べるわけではないけれども、なにかに突き動かされて出てくる表現。それは、誰に向けられているのかも分からない。もしかしたら、祈るように、自分のなかのよく分からなさと向き合う行為なのかもしれない。それをわたしは藝術と呼びたい気がしてくる。ただし、佐藤さんであれ小森さんであれ、なんら特別な藝術家という殻を被った人ではない。なにかに突き動かされてしまった普通に生きる人間なのだ。藝術の種はどこにでもある。そんな藝術の種を人間はそれぞれ「自分の手で」育てて生きている。映画の驚くべきところは、そうした藝術家に限らない人間の営みを肯定出来てしまえることにある。しかし、その大切な慎ましさをわたしたちはよく忘れる。だからこそ堂々と当たり前のことを成し遂げた『息の跡』という映画が、わたしにとってとても大事な手紙だったように思えてくるのだ。
 『息の跡』
『息の跡』2016 年/ 日本/93 分/16:9
監督・撮影・編集:小森はるか
編集:秦岳志、整音:川上拓也
特別協力:瀬尾夏実
プロデューサー:長倉徳生、秦岳志
http://www.ikinoato.com
2017 年2 月18 日 (土) より、ポレポレ東中野にてロードショー、ほか全国順次公開
 writer:三浦 翔
writer:三浦 翔
1992 年生。大学院生。監督作『人間のために』が第38 回ぴあフィルムフェスティバルに入選、現在「青山シアター」にて配信中。理論研究と作品制作を往復しながら、芸術と政治の関係を組み替える方法を探究している。
Do It Myself(自分でやってやる)-自分だけが自分の支配者であること
が「D.I.Y.」という言葉を嫌いになったのは、些細なことがきっかけだった。大学1 年生のとき、原発について自分で調べてFacebook に投稿したら、先輩から「ナイスD.I.Y.」というコメントがきたのだ。そのとき僕は、なぜかムッとしたのだけど、それがなぜなのか、はっきりとわからないでいた。
現代社会において「D.I.Y.」は、自律性・自主性・主体性を重んじる標語として、好感をもって迎えられる。とある公立中学校では、学校教育の原理として「自立貢献」を採用しているそうなのだが、これはまさに「D.I.Y. の精神」と言えるだろう。例えば図書館に置く本を図書委員会が自分たちで選ぶ。お金を渡されて、エロ本以外ならなんでも買ってきていい。しかも図書委員会が欲しい本ではなく、クラスのみんなが読みたくなるような本を選ぶ。これはかなりの反響で、ポツポツと生徒がいるだけだった昼休みの図書館は今や満員となり、生徒たちは地べたにぎゅうぎゅうに押し合って本を読んでいるのだとか。これ自体はいい話である。
たしかに、このような「D.I.Y. の精神」による学校教育は日本にとって必要かもしれない。日本人の行動の傾向は「他人志向型」(リースマン)であるとよく言われている。みんなが空気を読んで判断し、周囲に目配せしながら行動する。僕が通っていた中学校も「他人志向型」がふつうで、友達の目を気にし、「正常さ」というものを勝手に想像する。みんなこの空気によって作り出された「正常さ」に従うようになる。誰も命令していないのに、誰もが従っている。そこから逸脱するものはなんであれ「異常」のレッテルが貼られる。ヤンキー、ガリ勉、ぼっち、のっぽ、デブ、チビ、女子みたい、等々。みんなが「自分は正常だろうか?」と自分に問い続け、精神をすり減らさなきゃいけない。これは教育の場だけでなく、日本の社会一般でよくみられることだ。このような空気を打ち壊す理念としての「D.I.Y. の精神」や「自立貢献」というのは、いかにも魅力的に映る。
しかし注意したいのは、「D.I.Y. の精神」や「自立貢献」という言葉が、新自由主義(ネオリベラリズム)という考えと一緒に主張されることである。日本における新自由主義的な政治は、1980 年代のなかばから公教育の改革というかたちでスタートし、少しずつ社会に浸透し、僕たちの考え方そのものをかたち造るようになった。新自由主義においては、すべてが市場における競争の論理で考えられる。たとえば新自由主義の理論においては、親が子どもに愛情を注ぐことを「投資」と考える。「個性」や「個人主義」を重んじる考えはけっこうだが、このように「個人」を一つの「企業」とみなして、あらゆることをビジネスの論理で片付けるようになってしまうのはどうなのだろうか。この考え方ではすべてが自由だが、同時にすべてが「個人=企業」の自己責任になる。もし貧困格差が生じても「貧乏なのは自己責任」ということになってしまう。6 人に1 人が月々約10.4万円で生活し、子供の貧困も8 人に1 人という日本の社会において、この考え方はあまりに酷だ。事実、新自由主義の理論による政治は、金持ちを儲けさせ、格差を拡大しただけだった。そういえば、あの公立中学校が掲げていた「自立貢献」は、イギリスで新自由主義を徹底したサッチャーの言葉だった。たしかに学校での教育を子どもたちに自由なものとしてひらくことは、聞こえがいい。しかし、自由はつねに責任とセットだ。子どもたちは、突然あたえられた自由の責任をすべて自分で負うことはできるだろうか。誰かに命令されてそれに従っているうちは、誰かのせいにできるけれど、自由にやれば誰のせいにもできない。すべて自分だけで責任を負うことは困難だ。
* * *
こうして考えてみると、「Do It Yourself !(お前が自分でやれ)」という命令文は、非常に冷たく響く。ふつう誰かが命令すればそのひとに責任が生じるが、この「Do it yourself !」という命令文だけは、逆に他人に責任を押しつけることになる。だから、指導権を持っている側の人間(先生や上司や国)がこの言葉を生徒や部下や国民に対して言うのなら、それは無責任で抑圧的な言葉になるだろう。僕が先輩に「ナイスD.I.Y.」と言われてムッとしたのも、このためだったのかもしれない。ではどうすればいいのだろうか。やはり誰かに従うのがよいのか。いや、僕なら「D.I.Y.」と他人から命令される前に、いっそのこと自分から「Do It Myself( 自分でやってやる)」と言い切ってしまうだろう。僕は、他人に向かって「D.I.Y. の精神」を急き立てるよりも、こっそり自分に「D.I.M.」を命じる。もちろんそれは困難な道だろう。すべて自分次第なのだから。だけど、自分だけが自分の支配者となるとき、はじめて自分自身をまるっと賭け金にした試みと冒険をはじめることができる。その困難な道のほうが、愉しいにきまっている。
 writer:牛田悦正
writer:牛田悦正
1992年生。革命のために政治理論史を勉強している。共著にSEALDs『日本× 香港× 台湾 若者はあきらめない』(太田出版)など。UCD 名義でラップをしており、現在Mixtapeを製作中。乞うご期待。
風が帆を導くところへ
僕にとって、ブラジルの音楽は常にとても遠くで鳴っているものというイメージがありました。それは、ブラジルと日本が物理的に離れていることを指しているわけではなく、基本的にポルトガル語で歌われていることや、今までアメリカやイギリスのポップスを中心に聞いていたせいか、メロディやリズム、節回しがすごく異質で独特なものに聞こえたことで生まれたイメージです。ただ、そういう「異質さ」みたいなものを段々と魅力的に感じていくようになって、僕は少しずつブラジル音楽の深い海に潜っていきました。
ただ、ブラジル音楽というのをどんなに聞き進めていっても、その「異質さ」が薄まることはありませんでした。どこか、すごく遠くで鳴っているもの、そのイメージも決して変わることはなかったのです。
しかし、ブラジルの内陸部であるミナス・ジュライス州出身のアーティスト、Fernando Oly の唯一のソロアルバム「Tempo Prá Tudo」を初めて聞いた時、いままで触れたことのあるブラジル音楽とはまったく違うものを感じました。
音像は全体的にリバーブがかなり効いていて、ミナス関連の作品の中でも特筆して浮遊感のあるアルバムになっています。ただ、そうした特徴とは別に、今まで聞いてきた他のブラジル音楽と違う印象を持ったところは、作曲者の手元がすぐそばに見えたような気がした点です。確かにとても遠いところで鳴っている印象や異質感はそれなりにあるのですが、同時にすごく傍に寄り添うような感じもしました。
前々回のBack to the CLASSICs で「個人的な音楽」ということに関して書きました。読まれていない方もいると思うので概要を説明すると、「一人で作曲しディレクションした音楽には、バンドや多人数で作った音楽とは違い、『共有』という段階を踏まないまま完成に向かっていく。音楽上のアイディア等だけでなく、作っていくなかで生じる様々な感情も一切共有することなく作られていくので、作者のパーソナルな部分がはっきり出やすく、特別な雰囲気を感じる作品になる」。こういった雰囲気を感じる音楽のことを「個人的な音楽」として書きました。
Fernando Oly のアルバムの中で演奏しているのは、Fernando Olyだけでなく様々なミナス出身のミュージシャンが参加しているのですが、このアルバムは間違いなく「個人的な音楽」です。それも、今まで聞いたことのある「個人的な音楽」の中でも特筆して「個人的」だと感じました。それはアルバムの中の声、コーラス、メロディやリズム、音像がそう感じさせるのだろうと思います。
とにかく、このアルバムを聞いて、ぼくは初めてブラジル音楽というものをすごく傍に感じることが出来ました。
そして聴き進めていくうちに、Fernando Oly も自分で実際に曲を作っているということに改めて気付きました。当たり前のことなのですが、他のミナス系のアーティストを聞いた時は、そんな当たり前のことに気が付いていませんでした。そんなはずはないのに、どこかからあらかじめ用意されたような音楽のように聞こえていた気がします。
僕が自分の部屋で何となくギターを弾いて曲を作ったり、詩を書いたりするように、Fernando Oly も自分の部屋やスタジオで創作活動をして、それを仲間と共有して、アレンジや録音をして完成させていく、そんな光景がはっきりと浮かびました。その光景は、本当に尊く、僕にとってすごく価値のあるものです。こういう光景を見せてくれる音楽と出会うときはいつも、何かが導いてくれたような気がします。
是非アルバムを通して聞いて欲しいですが、とりあえずアルバムの中でも特に好きな一曲と、僕が好きな他のミナス系のミュージシャンの曲を一曲紹介します。
Quando os Beatles voltarem / Fernando Oly
今回紹介したアルバム「Tempo Pra Tudo」のラストを飾る曲。繰り返し歌われる「Quandos os Beatles voltarem outra vez tocar(ビートルズが再び演奏したら)」という、ビートルズへの憧憬を歌ったラインが印象的な曲。音像は全体的にかなりドリーミーだが、ポップでメロウな仕上がりになっている。展開やリズムセクションもそこまで異質感はなく、繰り返し出てくる切ないメロディとコーラスのハーモニーが心地よく流れていく。
Clube da Esuquina N’ 2 / Lo Borges
Fernando Oly と同じミナス出身のミュージシャンLo Borges の傑作アルバム「A Via Lactea」からの一曲。最初から最後まで本当に切なく美しい曲。上で紹介したFernando Oly の曲に比べると、かなりはっきりした音像で録音されている。各パートの音も良く、特にピアノの音とフレーズが最高に美しい。ストリングスのアレンジもすごく映像的な感じがして素晴らしい。
ブラジル音楽をあまり聞いたことがない人の入門的な一曲としてもオススメ。
 writer:加藤寛之
writer:加藤寛之
1994 年生まれ。神奈川県葉山町出身。趣味は楽器を演奏すること。毎回テーマに沿って選曲をしていく予定。「すばらしか」というバンドでベースを弾いてます。
喜びの哲学者
十七世紀、今からおよそ四〇〇年前にオランダに生まれたスピノザという哲学者について少し書いてみたい。
彼は『知性改善論』という本の中でひとつの決心をする。それは、わたしたちが途切れることのない最高の喜びを享受できるようなものが存在しないかどうかを探求してみよう、というものだ。
最高の喜び。あるいはそれを幸せと言い換えてもいいかもしれない。最高の幸せ。しかもそれがずーっと続く。普段頑張っている自分のためにちょっとご褒美、とかそんな生半可なものじゃない。なぜなら、求めるのは最高の喜びなんだから。しかし、果たしてそんなものがあるのか。あるかもしれないけど、ないかもしれない。もしあったなら、それは最高の結果と言える。けど、なかったら。本気でそれを探求するためにはある程度何かを犠牲にしなくちゃならない。お金持ちになるのを諦めなくちゃならないかもしれないし、有名な人になってちやほやされる可能性を捨てなくちゃならないかもしれない。でも、そうしたものを捨てたとしても、最高の喜びが見つかるかどうかはわからない。そもそもあるかどうかもわからないのだから。
だから、これは賭けだ。スピノザは最高の喜びに賭けた。そして『エチカ』という一冊の本が書かれた。果たして、スピノザの賭けはどうなったのか。
この本は歴史の中に埋もれることなく生き残った。そして時間も距離も遠く隔てた四〇〇年後の日本で、手にとって読むことができる。これは驚くべきことだ。そしてこのことが、この本のすごさを証明しているとも言える。試しに、最後の一文だけ引用してみよう。
とにかくすぐれたものは、すべて希有であるとともに困難である。
残念ながら最高の喜びはありませんでした、とは書かれていない。つまりそう、最高の喜びはあるのだ。ただし、それに至るまでの道のりは困難で、とても簡単じゃない……。
だから実際、『エチカ』も簡単に読めるような本じゃない。最高の喜びを証明するために、まるで数学の証明をするかのようにとても緻密に書かれている。一ページ目から挫折しそうになる程だ。けれどスピノザは、わたしたちも最高の喜びに至ることができるように『エチカ』を書いている。だから、ひとまずスピノザを信じて読むことだ。スピノザは喜びを善いことだと言っている。その反対に、悲しみを悪いことだとも。そしてそもそも喜びというのは、自分の活動力、生きるためのエネルギーを増大していくことだと言っている。だから喜びの反対の悲しみは、活動力を減少してしまうことだというわけだ。
生きていく上で、人の身体は様々な刺激を受けている。活動力を増大するためには、自分が喜ぶような刺激を受けることが必要だ。スピノザは、味のいい食事や香水などのいい香りを楽しんだり、音楽を聴いたり、スポーツを楽しんだり、おしゃれをしたりすることなどを推奨していて、そうした喜びの刺激を身体に受けさせることで自分のエネルギーを高めていくことが賢い人の生活方法だと言っている(ただし、飽きるまでやってはいけない。なぜなら飽きるということはすでにそれを楽しんでいないから、と一応釘もさしている)。
こう聞くと、なんだそんな簡単なことでいいのか! と思ってしまうかもしれないが、もちろんそれだけじゃない。大事なことはまだある。それは、刺激に対して能動的になることだ。能動的というのは受動的と対になっている。言い換えると、する/されるのことだ。喜びのためには能動的になる必要がある。自分の好きなものやことなど、自分がどのような刺激を受ければ喜びになるのかを知って、それに基づいて行動すればそこにはエネルギーが生じる。けれど反対に受動的でいることで周囲に翻弄されたり、自分には合わない刺激を受けて消耗してしまうと、それはエネルギーの減少=悲しみになってしまう。
そう考えると、大人になり社会に出ていろいろと我慢を強いられたりするのは喜びとは程遠いことのようだ。けれど、そういうときにスピノザを思い出して自分が受動的になっていないか、悲しみに暮れていないかを点検する。生きていく上である程度は受け身にならざるを得ないのはしょうがないとして、それでもそこから喜ぶために能動的に振る舞うことができないかを考えてみる。そうするだけでも心は少し軽くなる。
とりあえず以上のことは、スピノザが『エチカ』の中で書いたことをわたしたちの生活にグッとひきつけてみたエッセンスのようなものだ。これだけではまだ最高の喜びには全然届いていないし、そこに届くためにはこの他に通らなくてはならないいくつものプロセスがある。わたし自身、それらすべて理解しているわけじゃ全くない。けれど、最初から困難だとわかっているのならゆっくり進んでいけばいいだけの話だ。この、喜びの哲学者が示してくれた、人生を喜びに満ち満ちたものへと形づくるための道すじを。
 writer:小林 卓哉
writer:小林 卓哉
1992年生まれ。大学在学中、保坂和志とロラン・バルトに感銘を受け文学に強い興味を抱く。
現在都内で販売員をする傍ら執筆中。
関連イベント
CLASSICs Session for U25 vol.1 関野吉晴 『D.I.Y. を生きる』
6/17(土) Talk 14:00-16:00
Party 16:00-17:00
会場:代官山 ティーンズ・クリエイティブ
ゲスト
関野吉晴 『D.I.Y. を生きる』
詳細はこちら