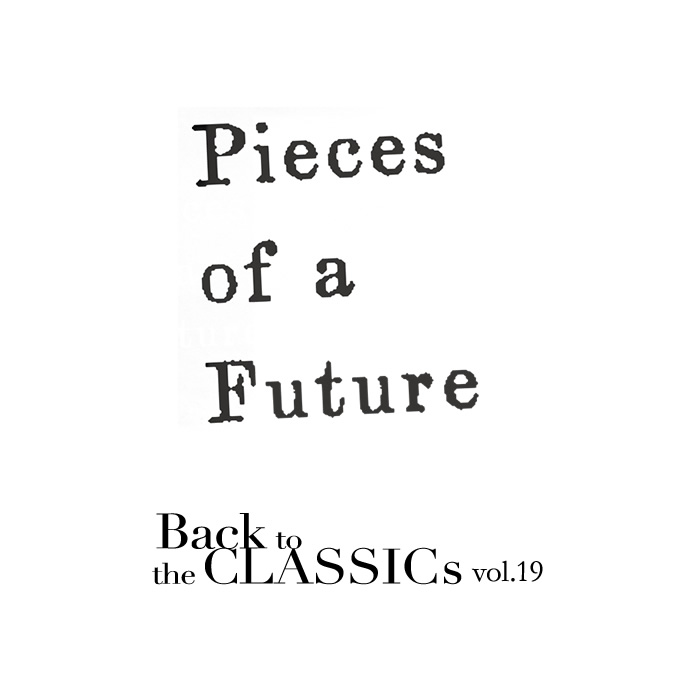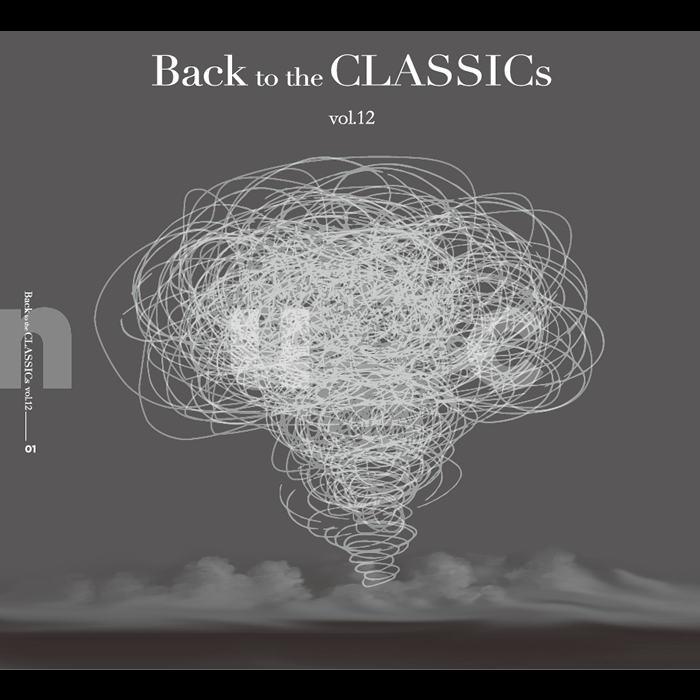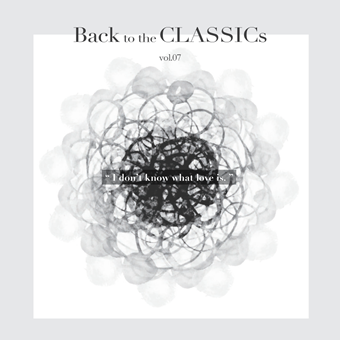Back to the CLASSICs vol.10
アートは役に立つのか?
アートは役に立つのか?そんな問いを立てるとき無意識に前提としているのは、アートを何かに利用したいという欲求であることが多い。たとえば、巨大な音楽イベントでの経済効果、アートの政治的利用、アートによる地域興しなど。いわゆるネットサヨクが政治を忌避するアーティストを叩くとき、僕はどうしても心が痛い。アートがなにかに利用されることへの抵抗感も分かるし、同時に(アメリカのように)アーティストこそ声を上げて欲しいと思っている人たちのこともよく分かる。この分断、問題はどこにあるのか。
鶴見俊輔という戦後民主主義を代表する知識人がいる。彼は信念と態度を分けて考える。信念とは、民主主義や共産主義などといった価値のことであるが、それより深い根のレベルに態度を置き、信念と向き合う人間の態度を考えようとする。それは簡単にまとめて言うならば、戦後の人間にとって、侵してしまったこと、受けた傷、自分が加害者でもあり同時に被害者でもあった複雑な記憶のことである。『限界芸術論』をはじめとした彼の芸術論のなかには、小説やマンガ、民衆の歌のなかにそうした記憶を共有する可能性を探ろうとしていたことが読み取れる。鶴見流に考えるならば、意見を表明する前に個人が繰り返し立ち返るような強い態度=足場を育むことこそアート=芸術の使命なのである。それがなければお互いがどういう人間であるかを明らかに出来ないだろうし、批判的コミュニケーションと呼ばれるものなど形式的なものに過ぎなくなってしまう。
本来芸術の仕事と役に立つ仕事は別ものである。だからといって、それが政治や現実の社会から逃げる理由にはならないだろう。むしろ、鶴見の言う信念と態度を明確に分けることこそが、いま議論されている信念を柔軟に捉えることを可能にし、行為と発言の空間へアートを接続することを可能にするはずである。こうした点を、いま誰もが再確認するべきではないか。
文: 三浦翔
2 万年前の「芸術家」の子どもたち、その芸術について。
人類が初めて作り出した最古の芸術作品と言われるラスコーの洞窟絵画について教わった時のことだった。
“ラスコーの絵画、人類で初めて芸術を作った人たちを考えて、「なぜ人は絵を描いたのか?」と人は問う。それに対して儀礼のためにとか、「~に役に立つから」と事後的に推測して答えるのは間違っている。そうではなくて、絵を描き、芸術を作り始めたものたちが、「人」になったのだと捉えなくてはならない。だから、「なぜ人は芸術を作ったのか・・・何のために?」という問いの立て方はそもそも間違っている。芸術を生み出したからこそ、それ以来「その者たち」は、人となった。”
こう聞いて、シンプルに感動した。本当にそうだと思った。先生の話は哲学者カントを引きつつこう続いた“すべての物に目的や価値があるとされている。しかし、価値を与えられないもの、あらかじめ目的を持たない「役に立たないもの」がある。決して「~のために」と一つの目的に還元されない、意味をあらかじめは持たないが、だからこそ、それ自体が意味そのものであるものがある。それには意味はない、だが尊厳がある。”
聞き間違えていたかもしれない、しかし勝手に蒙が開かれたような気がした。それ自体が意味となる「無意味なもの」。そこには尊厳があるということ。ここから芸術のこと、そして人間のことを考えられると思った。この時から僕は芸術、例えば文学に「なんの意味があるのか」としたり顔で問われて、確信があるのにうろたえて口ごもる弱い瞬間はなくなった。
なんのために生きているのかわからなくなって迷う、そうして暗い夜に耳を澄ましていると、特に意味を答えようもない「芸術作品」である一つの歌に心を動かされていつのまにか明日を迎えられているとき、意味を・目的を持たない自分に尊厳の小さいかけらが光るのに気づく一瞬がある。そのようなもの、問いようもない無意味さから尊厳を生み、それ自体が新しい意味になるもの、それが芸術なんだと信じている。
芸術とは何かを考える時もう一つ大事にしている考え、“生きることに必要のあるもの。正気に耐え難いから新しい正気を作るためのもの。それが、例えば芸術です“という言葉を、何度も読んだ本から拾ってノートに書きつけてある。毎日は嘘だと思いたいニュースに溢れていて、疲れて無力感ばかりが積もる。そんな時だからこそ、そこに新しい正気を、新しい意味を産み出すための芸術が必要なのだと思う。けれど、それをわかっているのを承知した上でまだ、無理っぽいと思ってしまう時はある。そんな時に、これまでなんとか生み出して来た「人」たちがいたことにまた背中を押される。完成させられないまま、自らが信じる芸術を作る冒険をやめなかった20世紀最大の芸術家の一人の姿を記した本を読む。自分自身も、「芸術」を生むことで人間になったものたちの末裔であるとするのなら、その約2万年後の20世紀に生まれて、それを産み出すことをやめていなかった芸術家から勇気を得ることはきっと間違っていない。
“しだいに大きくなる絶望に襲われながらも、「ともかく続けなければならない、放棄してはいけない。」そう言って彼は勇気をふるいおこす。/「駄目だ、筆がうまく動かない。」「自分には才能がない、それ以上に勇気がない、才能がなくてももう少しの勇気があればいいのだが。」「もうどうしていいかわからない、畜生!」/ それからまたほとんど叫ぶようにいう。「もう少しの勇気、五十グラムの勇気、あと一滴の勇気さえあればいいのだが!」”
こうして進み続ける、一滴の勇気をふりしぼって。うまくいった気がする。一瞬の後に到達出来ないのに気づいてすぐに消す、作りなおす。それを繰り返す。何度も。
“いままで何をしていたのだろう。ここから始めるべきだったのだ。いよいよ始まる!”

ジョルジュ・バタイユ 出口裕弘 訳
『ラスコーの壁画』
二見書房 1975 年

佐々木中 著
『切りとれ、あの祈る手を』
河出書房新社 2010 年

矢内原伊作 著
『ジャコメッティ』
みすず書房 1996 年
 神宮司 博基
神宮司 博基
1989年東京生まれ、音楽の好きな青年。大学院生。 Fethi Benslama、フランスのムスリム系移民の研究。本を読み、良い音楽を掘り進め探す毎日。
ひと月ほど仕事が休みになった、ほとんどの時間を動かずに過ごしている。
あの人の名前を決して私の前で口にしないでください。ひざまずかずにこの名前を口にするのは冒涜のように思われるのです”(レーモン・ルーセル)
ルーセルがこう語った「あの人」とは、ジュール・ヴェルヌのことである――と一息に書いてしまうことのなんたる野暮!、だが、ルーセルにとってヴェルヌはそれほどに、特別だった。耳にするだけで指先まで動揺が走り、軽い気持ちで人に薦めることはもとより、声に出すことも少しも容易でない名前を、誰しも持っているものだろうか。
決定的な徴をもたらす経験――恋心とは、いつもそういうものではないか。軽く口にできる名前などというのは、あくまで「好奇心」の対象であり、惚れ始めた人の名前を易々と風潮する人はいない。そしてそのような秘めやかさ、淫靡さを伴わない作品との出会い――読書であれ、他の芸術であれ――が、人を変えることはない。
レヴィ=ストロースは『悲しき熱帯』の冒頭で「私は旅や探検家が嫌いだ。それなのに、いま私はこうして自分の探検旅行のことを語ろうとしている。だが、そう決めるまでにどれだけ時間がかかったことか!」と書く。いかにもこれは好奇心に突き付けられた否である。他者への開かれ、愛を何よりその礎とする人類学者たる彼の作品は、この言葉から書き始められなければならなかった。
私の育った町はいわゆる観光地だった。毎年、連休中だけ実家の前の道路が渋滞する様を眺め、その度に言いようのない苛立ちを覚えていたことを思い出す。幼いながらも、あの観光客たちの眼差しと排気ガスが、私の住む風景を愛するわけでなく、強姦し、蹂躙していくだけに見えていたのかもしれない。――と、推量の形で書くのは、もはや他人と言って過言でない過去の私への配慮からである。
旅好きな人とは話が合わない、という自説がある。ルーセルはよくキャンピング・カーで世界各地を旅したという。しかしその間中、カーテンを下ろして読書に耽っていたらしい。
“ところで私は、これまで一度も、これらの旅行を、私の本の素材にしたことがない。このことは、私にあって、想像力がすべてであるという事実を示している点で、指摘しておく必要があるように私には思われた”(ミシェル・レリス『レーモン・ルーセル―無垢な人』)
ルーセルは「現実」と「言葉」が結び付いてしまうことを嫌ったようだ。ルーセルの言葉は決して現実を説明しない。言葉はいつも、言葉そのものだった。
“これまでの生活で、あんなに何度も現実が私を失望させたのは、私が現実を知覚した瞬間に、美をたのしむために私がもった唯一の器官であった私の想像力が、人は現にその場にないものしか想像できないという不可避の法則にしばられて、その現実にぴったりと適合することができなかったからなのであった。”(マルセル・プルースト『見出された時』)
言葉とは何か、と問うた人は数多いる。が、未だにこの問いから人が解放されているとは言い難い。読み、そして書くという秘儀は、いついかなる場合でもその不自由と不可能を生きるということであり、その怖れを欠いてしまえば、人は容易く言葉を所有し尽くせるという思い込みに捉われてしまうのではないか。そしてすぐに「意味」や「説明」ばかりを求めてしまう。
言葉が人間よりも先にあったということを、私は疑わない。私たちが言葉を生み出し、用いているのではなくて、私たちの方が言葉に用いられている。銀河のなかに身を投げ出され、滔々たる言葉の飛沫を肌に受ける。書く時、私たちは自らの欠如を差し出さなければならない。自らの穴を差し出さなければならない。その無意味と無根拠を、引き受けなければならない。

クロード・レヴィ=ストロース著 川田順三訳
『悲しき熱帯』

レーモン・ルーセル著 岡谷公二訳
『アフリカの印象』
平凡社ライブラリー 2007 年

ミシェル・レリス著 岡谷公二訳
『レーモン・ルーセル―無垢な人』
ペヨトル工房 1991 年

マルセル・プルースト著 井上究一郎訳
『失われた時を求めて10 第七篇 見出された時』ちくま文庫 1993 年
 writer:三嶋 佳祐
writer:三嶋 佳祐
ゆだちというバンドで音楽活動、アルバム『夜の舟は白く折りたたまれて』を全国リリース。音楽、小説、美術など様々な制作活動で試行錯誤。書物、蒐集、散歩、アナログゲーム、野球を好む。広島カープのファン。
黄金の言葉が孤独を痛打する
詩は難解で分からないもの、というのが通念としてあるように思う。私もそう思っていたが、最近になって味わえるようになった。そのひとつの要因として、社会に出て働くようになったことがあるように思う。
毎日交わされる差し障りのない会話に鬱憤が溜まったので、詩を読んでみたのだ。詩とは、誰に通じるとも分からないままに限界まで研磨された言葉たちだ。誰にでも通じるような言葉のやりとりに疲れたので、だから詩を読んでみたわけだ。すると、ある種の快感を伴って詩が読めるようになっていた。中でも吉増剛造という詩人の書いたものは強烈だった。
「珈琲皿に映ル乳房ヨ!」から急激にギアが上がり、次の「転落デキナイヨー!」というカタカナ表記が悲壮で滑稽な感じを醸し出し、「剣の上をツツッと」で少し減速しながら最後の「消えないぞ世界!」という叫びで再び一気に爆進する。ここまで言葉に音楽を感じるのか、という驚き。
私にとって決定的だったのは次の「燃える」という詩だ。
言葉の連なりの圧倒的な格好よさ。「太陽とリンゴになることだ」という一行だけ見ればどこか陳腐な感じがしないでもない。だが「似ることじゃない」とそれに付け足すことで「太陽とリンゴになる」という「僕の意志」に迫真性が生じている。次の乳房、太陽、リンゴ、紙、ペン、インク、夢という語が矢継ぎ早に繰り出される一行と、それにかかる「凄い韻律になればいいのさ」とやさしく響く一行が生むリズムの緩急もたまらなく心地よい。
そして最後。「今夜、きみ」と語りかけるように始まり、「スポーツ・カー」のスピードが「流星」という天体のスピードに移り、それが正面から、刺青が顔に彫り込まれるように衝突するその衝撃と「きみは!」という叫びのような問いかけで締めくくられる四行。このイメージと、この疾走感。
これを読んだとき、私は打ちのめされてしまった……
以来、私は鞄に詩集を一冊入れて過ごしている。周囲の環境に違和を感じるのなら詩を読んでみるのがいい。一見、誰からの理解も拒んでいるように思える詩が、それゆえ孤独を感じる人間の伴侶となることがあるだろう。それがたとえ若い人間の、後になって振り返れば他愛なく思うに違いない青春の、ほんの一時であったとしてもだ。
アア コレワ
なんという、薄紅色の掌にころがる水滴
珈琲皿に映ル乳房ヨ!
転落デキナイヨー!
剣の上をツツッと走ったが、消えないぞ世界!
(「朝狂って」より一部抜粋)
僕の意志
それは盲ることだ
太陽とリンゴになることだ
似ることじゃない
乳房に、太陽に、リンゴに、紙に、ペンに、インクに、夢に! なることだ
凄い韻律になればいいのさ
今夜、きみ
スポーツ・カーに乗って
流星を正面から
顔に刺青できるか、きみは!
(「燃える」より一部抜粋)
 吉増剛造 著
吉増剛造 著
『黄金詩篇(思潮ライブラリー[名著名詩選])』
思潮社 2008 年
 writer:小林 卓哉
writer:小林 卓哉
1992年生まれ。大学在学中、保坂和志とロラン・バルトに感銘を受け文学に強い興味を抱く。
現在都内で販売員をする傍ら執筆中。
渚のわたし / 渚にて
この曲には二つのバージョンがあります。一つはこの曲のソングライターであり、渚にてのギター, ボーカルの柴山伸二さんが歌っているバージョン、もう一つは柴山伸二さんの妻であり、渚にてのドラム, ボーカルを担当している竹田雅子さんが歌っているバージョン。どちらのバージョンを聴いた方が良いのかと聞かれたら「どちらも」と答えるだろうし、どっちがより好きなのかと聞かれたら「どちらも同じくらい好き」と僕は答えるでしょう。ただ、どちらのバージョンがこの曲の本質を表現しているだろうか?と言われたら、ぼくは間違いなく竹田さんが歌っているバージョンを選びます。
Pastels のスティーブンパステルは、「渚にては柴山伸二と竹田雅子が分かち合っている共通の幻なのではないか?」と、あるインタビューで柴山さんに問いました。それに対して柴山さんは「渚にては僕と雅子の日常生活を通しての共通の現実を反映する場だと思っている。彼女をMuse と例えるなら、それはロマンチックな口説き文句ではなく、彼女が実際にそういう役割を果たした」と発言しています。
このやりとりに今回紹介した曲の全てが表現されていると思います。
曲中で繰り返し歌われる「渚のわたし、わたしの渚」というフレーズは、他の誰でもなく、竹田さんが歌うために用意されたものなのでしょう。それくらい必然性のある歌唱だと思います。
こんな切実な歌唱、歌詞、曲は世界的に見てもほとんど聞いたり見たりすることの出来ないものだと思うので、この記事を読んだ方は是非聞いてみて下さい。
最後に歌詞を一部抜粋します。
ああ 沈みかけた船を見捨てて 疲れ果てた馬に乗るの
そんな夢の通りになるの そこから先のことはもう
分からないの
わかっているの
ああ 遠ざかる わたしの渚
渚のわたし
 渚にて
渚にて『夢のサウンズ』
Pヴァインレコード 2004 年
 『On The Love Beach』
『On The Love Beach』Pヴァインレコード 2000 年
 writer:加藤寛之
writer:加藤寛之
1994 年生まれ。神奈川県葉山町出身。趣味は楽器を演奏すること。毎回テーマに沿って選曲をしていく予定。「すばらしか」というバンドでベースを弾いてます。
幽霊たちの歌
昨日まで間違いのないもの
それからは埋めて 揺れる船を漕ぎ出した
流された家も そのままで
まだ帰れないまま 笑ってる
僕らが手を伸ばしたら
空洞の奥の方が滲み出すだろう
触りあって 確かめて
見つけあって 見せあって
本に残らないような朝を迎えよう
(「空洞」より一部抜粋)
「並べたら壊れて。言葉の森には出口はない。
きっと届かないから、終わりにするよ。かわり
にいつでも歌を歌う。伝わなくていいから」
(「だれでもない庭」より一部抜粋)
「この街では、流れない唄?」
『海の子どもしか、知らない唄!』
『君は知っているかい!』
『耳をすませば、聴こえるよ…。』
「遅く起きても良い朝とか、
途中下車して行く海とか…。」
『美しい日々ね。』
ここに帰ってくるまで、待っていて…
「夏がまだ終わらないね…。」
『明日には終わるかもね。』
(「どこにもない家」より一部抜粋)
長いこと、幽霊たちが作った歌を聴いていた。夜な夜な、本としての体裁が密かに整えられたCD ケースを開いて、本棚に埋め込んだスピーカーから。あるいはライブハウスで、あるいは2202 教室で。聴くたびにどこか懐かしい気持ちになるのは、僕らが幽霊たちを通して古い夏の記憶を共有しているからかもしれない。
幽霊たちの歌はいつも夏の匂いがした。ここには、終業式以来ぶりの友達との再会を果たす夏祭りの夜のボウっとする湿度があり、好きな人との雨宿りの温度がある。そしてなにより、夏の終わりを惜しむ、時間の有限性への愛がある。「夏がまだ終わらないね…。」『明日には終わるかもね』。執拗に繰り返される無数の声が、夏の線分の先端を大切になぞっては、引き延ばそうとする。そうこうするうちに日が暮れる。水平線に浮かぶ夕日の、暮れゆきの最中に永遠が溶けていく。
ここには、純粋な音にもなれず、純粋な言葉にもなれない、懐かしさを届ける灰色の何かがある。ノイズでもあり、意味でもある何かが。それはまるで、突然の夕立の雨音であり、その下で笑い合う声だ。夏の終わりの漠然とした悲しみであり、それを惜しむ呟きだ。初恋の人への言葉にし難い想いであり、その告白の言葉だ。僕らを大切な人へとつなぎとめる淡い理由であり、その頼りなさからくる貴さだ。これを僕らは歌と呼ぼう。僕らに降り注ぐ時間を、余すところなく肯定する、熾烈な、幽霊たちの歌。これらの歌はすべての偶然性を救済する。あの、とりかえしのつかないものたちをも。
ゆだち『夜の舟は白く折りたたまれて』によせて。
 ゆだち
ゆだち
『夜の舟は白く折りたたまれて』
indienative 2015 年
 writer:牛田悦正
writer:牛田悦正
1992年生。革命のために政治理論史を勉強している。共著にSEALDs『日本× 香港× 台湾 若者はあきらめない』(太田出版)など。UCD 名義でラップをしており、現在Mixtapeを製作中。乞うご期待。