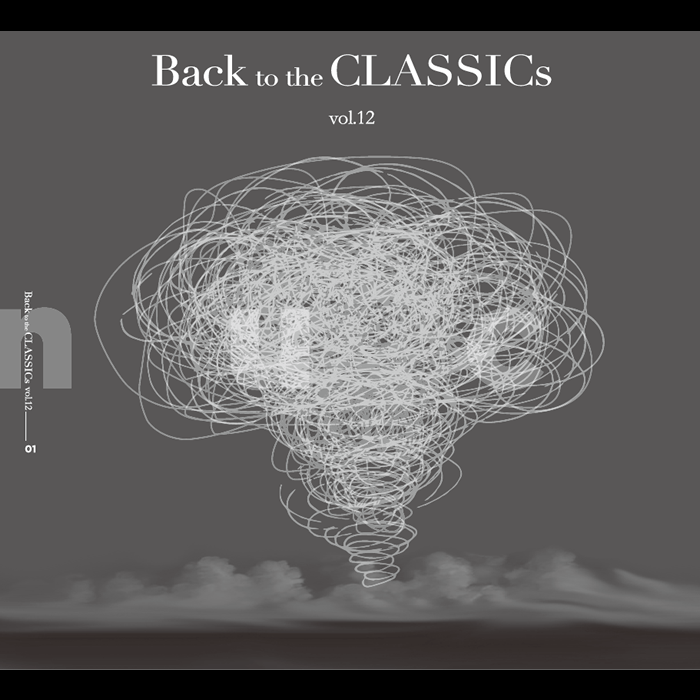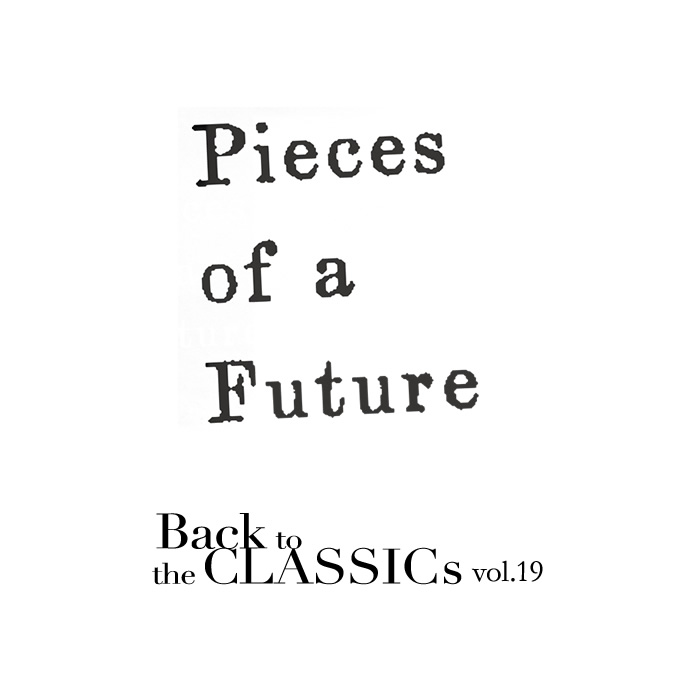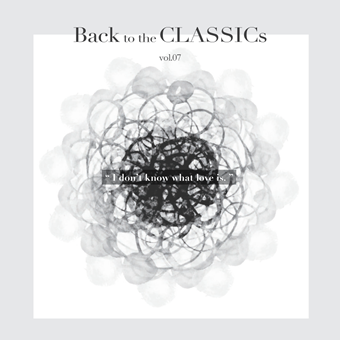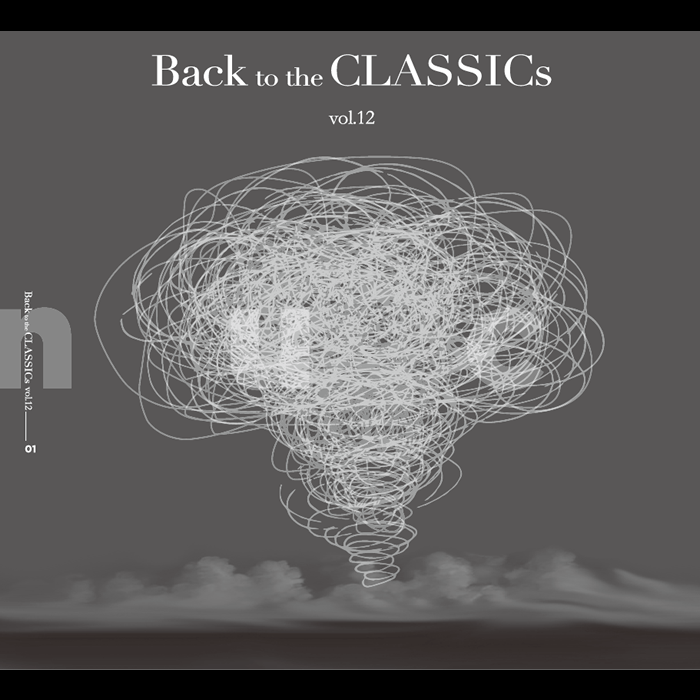
Back to the CLASSICs vol.13
今年7 月に国連で122 カ国の賛成によって核兵器禁止条約が採択され、ICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)がノーベル平和賞を受賞するなど、核兵器の禁止と廃絶を求める国際的な世論は高まっている。
一方、唯一の被爆国であるはずの日本の政府は核兵器禁止条約の交渉にすらのぞまず、批准を拒否し、ICAN の平和賞受賞にはコメントを出していない。それどころか、アメリカの威を借りて朝鮮半島を舞台にした核保有国の脅し合いに便乗し、「圧力」を強めよと緊張を高め続けている。
そもそも、「対話」と「圧力」という二項対立を疑わなければならない。テロの脅威が世界を覆う現在、自己の死を問わず殺人を犯せる人たちが存在しているのである。そんな状況下で「兵器」による「抑止力」は本当に「抑止力」か。それはいつどんなきっかけで引鉄を引き合う関係へ発展してもおかしくないではないか。
また、「核」は兵器や爆弾だけではない。「平和利用」という名の脅威の矮小化によって「原子力」のラベルを貼ったそれだ。絶対安全を掲げながら、首都の近くには決して建設されない発電所。欺瞞は明らかである。兵器だろうが発電所だろうが同じものだ。私たちの住む列島は大量殺戮兵器を抱え込んでいる。
核とは何か。二度の原爆投下と、原子力発電所の事故を経験した私たちの国が向かうのはどこか。経済的な都合、目先の利益などを超えて考えなければならないことは何か。私たちは想像力を来るべき未来まで届かせなければならない。
核時代という歴史の終焉を生きる私たちが、それでもなお読み、歌い、観て、想像し、永遠に終焉を先延ばしにする為の道具は、過去の偉大な作品の中にあるはずである。

『核の脅威- 原子力時代についての徹底的考察』
ギュンター・アンダース
青木隆嘉訳 ( 法政大学出版局)2 0 1 6 年
わけあって最近、通りすがりの人から「放射線」という言葉が発せられるのを耳にする場所にいる。そのうちの多くが、例えば、「放射線ってなんだっけ?難しいね」「目には見えないエネルギーなんだって」「私たちにも出せるのかな?放射線」といった無邪気な言葉である。誤解のないように付け加えておけば、ここは2017 年の東京である。
人は目に見えないものを信じることができない。だから多くの人は幽霊を信じないし、信じている人も大抵は「見たから」「見えるから」と言う。
たとえこの目で見たとしても、信じられなくなることもある。それは過去だ。
人は一秒毎にその切実さを忘れる。何を見たのかさえ曖昧になる。この世に生を受ける以前のことに至っては、知る術も限られている。
未来の出来事も同様に、いかにも実現しそうなことであっても、目前で起こるまでは心の何処かでは疑ったままだ。私たちは明日起こってしまうかもしれないことを( まさに「かもしれない」という言葉の通りに) 信じていない。いや、信じることができない。現在以外のことは、手に負えないことなのだーー本当にそうだろうか?
ギュンター・アンダースという人が書いた『核の脅威ー原子力時代についての徹底的考察』という本が昨年、邦訳された。20 世紀に書かれたものだが、ここに書かれている状況は私たちの生きる現在においても変わっていない。どんな状況か。
例えば、ボタンを一つ押すだけで核ミサイルが発射され、人類が核戦争によって絶滅する危険性の下で生きていること、それは明日起きても全くおかしくないこと、核による被害はその規模の大きさから誰もがもはや脅威として認識できないこと、核は存在するだけで私たちの「行為」なのだということ、そこに主体として挿入される人間はもはや「行為者」ではなく、悪意のない「従業員」であり「起動装置」であるのが関の山であることーー等々。
そう、核時代においてはただ生きていることが罪なのだ。誰もがまともに信じることができない人類の終焉を、想像できないはずのそれを、想像できない故に罪である時代。誰もが「悪意のない殺人者」であり、誰もが「憎悪のない被害者」でもあるような時代。
この状況はこの先、世界中の核兵器が放棄され、原発が廃炉になったとしても変わらない。人類はその技術を発見してしまったからである。無くしても、またいつか作り出せる。
どころか、1945 年の広島と長崎を見たはずの私たちの国でさえ、核の「平和的利用」という言葉でその本質を誤魔化しながら技術を使用し、「原子力」と呼び名を変える手口まで用いて事態の「矮小化」に邁進している。
無理もない、私たちは現在見えていることしか信じられないのだから。事故が起きたとしてもすぐに忘れてしまうだろう、あんなことがあったばかりなのに「放射線ってなあに?」と宣う人たち……だって放射線は「見えない」のだから……私たちはそういう生き物なのだ、などと喚き散らすのは容易い。が、アンダースは決してそのように怯えきった幼稚な絶望や悲観を垂れ流す為にこの本を書いたのではない。
ここにあるのは、私たちはどのようにして最悪の未来を信じることができるだろうか、という問いだ。そしてそこから、いや、それ以前である今ここから、何を始められるだろうか。
"ーーノアは言葉を続けた。「わたしがここへ来てみんなの前に立っているのは、わたしにひとつの任務が課されているからだ。この酷い状態が起こらないように先手を打つのがその任務なのだよ。ーー時間を逆転させるのだ、苦しみを今日のうちに先取りし、前もって涙を流すがいいーーという声が聞こえたのだ。子供のときに父親の墓で唱えるために覚えた死者のための祈りを、明日死ぬ息子たちのために、そして決して生まれてこない子孫のために唱えるのだ。明後日では遅すぎるからだよ。ーーこれが私の任務なのだ」。"
 三嶋 佳祐
三嶋 佳祐
ゆだちというバンドで音楽活動、アルバム『夜の舟は白く折りたたまれて』を全国リリース。音楽、小説、美術など様々な制作活動で試行錯誤。書物、蒐集、散歩、アナログゲーム、野球を好む。広島カープのファン。

『小説集 夏の花』
原 民喜
(岩波文庫)1 9 8 8 年
悲惨な光景、地獄、非人間的な世界。かつて日本が直面した原子爆弾の投下という出来事を形容する様々な言葉たちは、たしかに間違ってはいないだろう。が、しかしそうした形容を伴い語られるその出来事に対して、私の想像力は果たして追いつけているか。2011年3月11日、テレビで観たあの映像ー人も家屋も車も、街全体が無慈悲に波に飲まれていったーは未だ記憶に新しい。しかし私はそのとき生きていて、画面越しにその光景を眺めていただけだった。都心にいた私は交通機関の麻痺により、一夜を外で過ごしただけでよかったのだ。それは私にとっては単なる非日常だった。その後、今にあの大災厄が私にも降りかかるとしばらく余震に怯えて暮らしたが、結局、今に至るまでそれが来ることはなかった。「 それ」が来てしまった後の世界を私は知らない。
表題作である「夏の花」は、原爆投下からその後の数週間までを描いた文庫本で20 ページほどの短い小説だ。その中で語り手である「私」は、いくつかの回想と出来事、そして出会った光景に対しての印象を淡々と静謐な筆致で語っていく。だが、そこからは不自然なほど「心情」が抜け落ちている。
声を聞くまで知っている人物だと分からないほど醜く歪み膨張した顔、耳のあたりで一直線に刈上げられた頭髪は帽子を境に髪を焼きとられたのだということに気づく。命からがら逃げ延びた人たちも火傷がひどく化膿し蛆が湧き、衰弱していく。赤く焼けただれた死体。また死体。燃え広がる焔の熱さと喉の渇き、うだるような夏の日差しの中、診療を受ける列に並ぶこと。屍体収容所の臭い。ふいに見憶えのある黄色の半ズボンを履いた死体を見つける。「真黒くなった顔に、白い歯が微かに見え、投出した両手の指は固く、内側に握り締め、爪が喰込んでいた」その死体は年端も行かない甥だった。それを見つけた父親。
そのような光景、出来事に直面するということは、一体どれほどの悲しみを伴うのか。恐らく言葉では言い表すことができない。慟哭すらすることができない。途中挿入された一節にこうある。
スベテアッタコトカ アリエタコトナノカ
パット剥ギトッテシマッタ アトノセカイ
あまりにも深い悲しみに涙も乾きはてた先。自らが遭遇したこの世界に起きた出来事が、果たしてあり得たことなのかを確かめるかのようにこの物語の語り手は「そのとき」のことを書き連ねてゆく。これは、「それ」が来てしまった後の世界だった。私の暮らすこの国では、かつて世界のすべてが剥ぎ取られてしまっていた。この事実。この事実に、向き合う必要がある。
毎年夏になれば黙祷を捧げる。戦争のために死んでいった人々を悼む。それはその犠牲の上に私たちが生きているからであり、そうして死んでいった人たちの無念さに痛み入るからだ。今を生きる私たちにはそうすることができる。だが、そこからもう一歩進もう。起きたことすべてを信じることのできない世界、つまりは世界への信がすっぽりと抜けてしまった世界を想像することだ。家族も死ぬ、友人も恋人も死ぬ、焼けただれて死ぬ。運良く生きのびても徐々に死ぬ。体には蝿が吸いつく。帰る家はもうない。どこにも帰れない。日常はない。痛みと乾きだけがそこにある。だが、これはあり得ていいことなのか? この世界は本当なのか?
もし想像力が及ばないのなら、読むことだ。私はそうする。身を切るような痛みに喘いでいたであろう先達の書き残した世界の中に束の間生きる。そこでは悲惨な光景を間近に目にすることになるだろう。だが、そこからは帰ってくることができる。帰ってきた後の世界は、おそらくまだ底が抜けてはいないはずだ。そこでどう生きるかは私に委ねられ、また同じようにあなたに委ねられている。
 小林 卓哉
小林 卓哉
1992年生まれ。大学在学中、保坂和志とロラン・バルトに感銘を受け文学に強い興味を抱く。
現在都内で販売員をする傍ら執筆中。
BOOKS

中央公論新社1996 年
クラシックとはその超時代性、普遍性の強度からそう呼ばれるのだとすれば、この漫画こそ相応しい。何の離れ業もなく、ただただ当たり前に反戦と反核を訴えた漫画。凡ゆる既成の価値に反旗を翻しながらも、歌い、踊り、絵を描き、本をつくろうとする芸術家、ゲン。私たちも彼のいた場所から始めなければならない。彼が生きた爆心地から。「原爆は絶対になくさんといけんのじゃ そのためなら、わしゃ何回でも本をつくって みんなにみせてやるわい」
Selected by 三嶋 佳祐正

ジャン=ピエール・デュピュイ(嶋崎正樹訳)
岩波書店2011 年
大惨事はなぜいつも「想定外」なのだろうか。たとえば「核爆弾の脅威」と「原発の危険」ーーどちらも同じNuclear Power だーーは知ってはいても、ひとは「信じることができない」。もしリスクがあっても事故が(戦争が)起こるまでは、まさかそれが自分の身に降りかかるとは思いもよらず、気づけばもう破局のさなかにいる。大惨事とはそういうものだ。では、どうすればいいのか。
Selected by 牛田 悦正

田崎晴明
朝日出版社2012 年
2012年当時、煙幕のように並べられた原発関連図書コーナーにあってひときわ光っていた本。ほとんど全ての本が原発の「危険」と「安全」を煽るなか、この本はそうした煽りを退け、中学生にでも読めるようにわかりやすく、かつ誠実に「放射線が何であるのか?」ということを解説してくれている。しかもインターネット上で、無料で公開されている。
Selected by 牛田 悦正
Movie

ロバート・アルドリッチ
1977 年(アメリカ)
日本も核武装しなければ核の脅威に立ち向かえないと思い込む人たちに欠けているのは、一人一人の人間が執り行う政治・外交のリアリティだろう。たとえどれだけ政治不信に陥ろうとも偉大なアメリカ映画がわたしたちに教えてくれるのは、政治のドラマであり、人間のリアリティである。真のサスペンス映画は爆弾を一つも爆発させずに、わたしたちを一瞬で凍りつかせる。最も怖いのは人間であり、逆に窮地を救い出すのもまた人間なのだ。ベトナム戦争終結後、ミサイル基地に潜入した元軍人と大統領の駆け引きが凄まじい政治サスペンスであるが、ここで描かれている普遍的な人間の駆け引きは、冷戦以後の世界にも未だに多くを語るだろう。
Selected by 三浦 翔

船橋淳
2012 年(日本)
かつて『ベトナムから遠く離れて』というドキュメンタリー映画がフランスで制作されたが、そこで問われていたのは、「遠く離れた」フランスの地からベトナムで起きている戦争のことを他人事と見なす、わたしたちの眼差し=距離を問い直すことであった。『フタバから遠く離れて』というタイトルからは二つの意味を読み取ることが出来る。ひとつは原発事故後に福島県双葉町から「遠く離れて」避難しなければいけなかった人たちのこと。ふたつめは福島から遠く離れた土地でこの映画を見ているわたしたちのこと。福島で起きたことは東京の問題である、という監督の強い意志をこのタイトルから感じられる。震災から早一年で制作・公開されたこの映画のことを考えると、原発事故以後の世界を日常にしてしまったわたしたちの感覚をもう一度問い直させられてしまう。
Selected by 三浦 翔
Music

寺尾紗穂
Album『青い夜のさよなら』より2012 年
原発の日雇いで放射能で被曝したおじさんが
虫けらみたいに弱るのを
都会の夜は黙殺する
私は知らない 人を救う術を
私は知らない 何にも知らない
私は知らない きれいな未来を
あるのは泥のように 続いてゆく日々
泥の上に花を 咲かすその術を
私は知らない
私は知りたい
Selected by 三嶋 佳祐

Gil Scott Heron
1977 年
「革命はテレビには映らない」と歌ったギルスコットヘロンが世界初の炉心融解事故にショックを受けて、未来のエネルギーと言われた原子力発電所についてNOを突きつけた歌。黒いディランと言われた詩人は誰よりも早く反原発ソングを歌った。1977 年から、今も全く古くなっていない。「デトロイトから30 マイルのところに、巨大な発電所が建っている。毎晩都会が眠ってる間にも絶滅までの秒針を刻み続けている。しかし、誰も足を止めて人々のことを、どう生き残るかについて考えようとはしない。そうしていま、僕らはデトロイトを失いそうになった。この狂気を、どうすれば乗り越えることが出来るだろう?」
Selected by 神宮司 博基

ANOHNI
Album『Hopelessness』より2016 年
Antony and the Johnsons のアントニー・へガティが改名し、女性となってからのアルバム。ドローンによって撃たれ、亡くなってしまった確かにいる「誰か」の声が歌になって届いたかのよう。続く曲では、もしイエスが現代に降りるならばどうなるか歌う。鋼鉄で囲われ、夥しい原子力発電所に覆われた地を見てしまったイエスは神に向かってこう言う、「あなたの未来は欲しくない。私は二度と、二度と戻らない」。「希望のないことHopelessness」と題したアルバムで、この時代の悲しみの部分を直視することからしか、「未来」などないことを教えてくれる。
Selected by 神宮司 博基
 牛田悦正
牛田悦正
1992 生。Rapper。ヒップホップバンド「Bullsxxt」のMC。1st アルバム『BULLSXXT』を10/18 に発売予定。著書多数。
 神宮司 博基
神宮司 博基
1989年東京生まれ、音楽の好きな青年。大学院生。 Fethi Benslama、フランスのムスリム系移民の研究。本を読み、良い音楽を掘り進め探す毎日。
 三浦 翔
三浦 翔
1992 年生。大学院生。監督作『人間のために』が第38 回ぴあフィルムフェスティバルに入選、現在「青山シアター」にて配信中。理論研究と作品制作を往復しながら、芸術と政治の関係を組み替える方法を探究している。